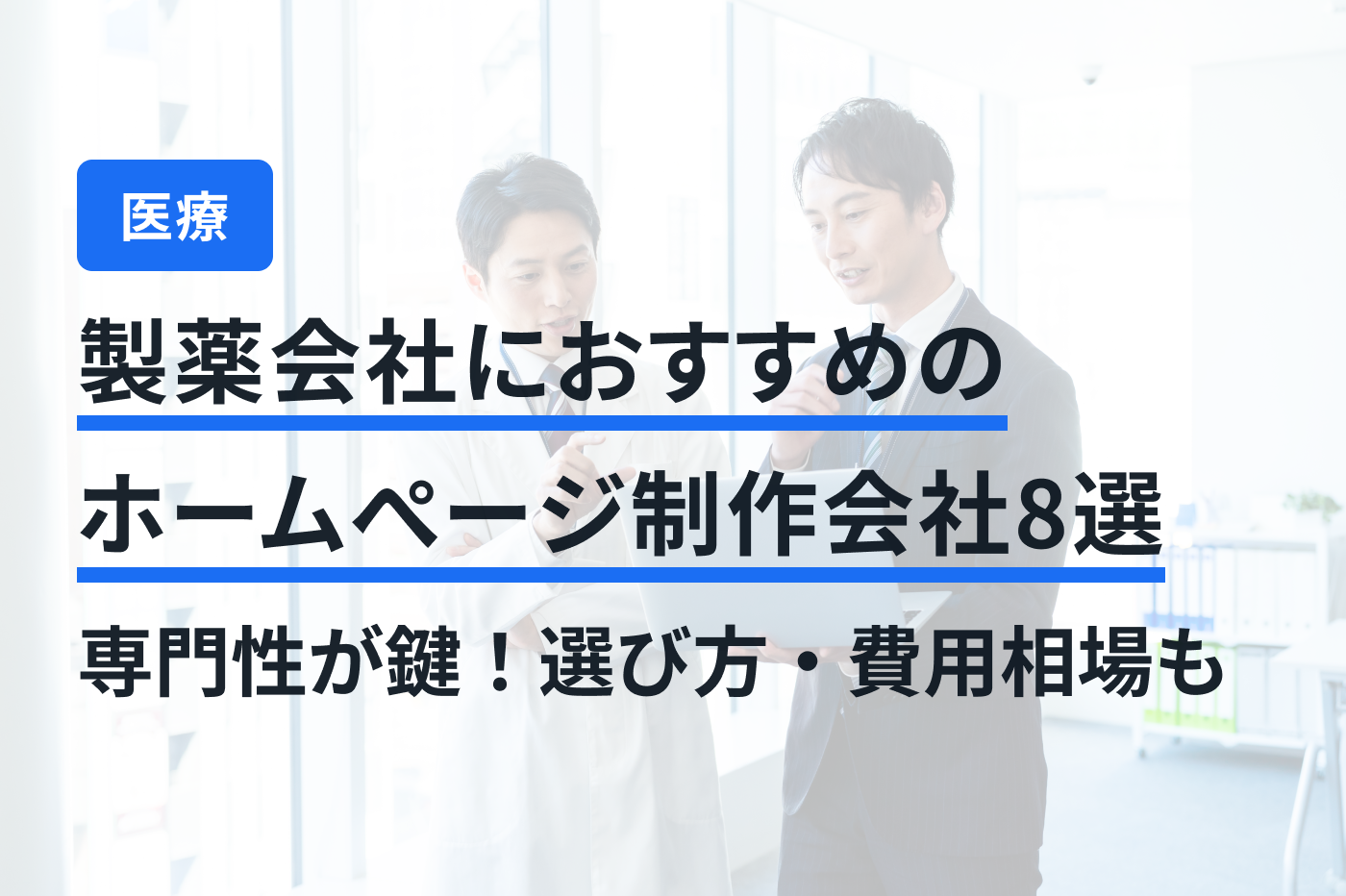医療機関におすすめのID管理システム5選|選び方と導入ポイントを解説
更新日 2025年11月27日
ID管理システムは、医療現場の安全と業務効率を同時に高める基盤です。誰がどの情報にいつアクセスできるかを一元的に制御し、電子カルテや検査系システムとの連携を通じて、安全・コンプライアンス・生産性の三立を現実的に支えます。
本記事では、医療機関に適したID管理システムの選び方と、おすすめのサービスを紹介します。導入時のチェックポイントも整理し、医療現場にフィットする最適なシステム選定をサポートします。
まずは、医療機関におすすめのID管理システムを厳選し、ご紹介します。特徴をわかりやすく解説しますので、ぜひシステム選定の参考にしてください。
COMPANY
株式会社Works Human Intelligence
出典:COMPANY https://www.works-hi.co.jp/products/hcm
COMPANYは、Works Human Intelligenceが提供するエンタープライズ向けのID統合管理システムです。人事情報と連動し、入退職・異動・兼務などに合わせて院内のアカウントと権限を一元管理できる点が特徴で、内部統制レベルの高い運用を支えます。
COMPANYは申請ベース/ルールベース/ロール��ベースなど多様な管理方式に対応し、医療現場の運用実態に合わせた権限付与・変更を設計しやすい構造になっています。棚卸や監査対応を前提にした機能がまとまっている点も医療向きです。
また、人事発令に基づくアカウントの自動メンテナンス、期限付き権限の付与、不要アカウントの検出や定期棚卸、外部委託・派遣スタッフのID管理などに対応。医療機関で起きやすい「退職者IDの残存」「短期雇用の権限付与漏れ」といったリスク対策にも有効です。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- 導入支援・運用支援あり
- 簡易検索
- 電話サポートあり
SmartHR
株式会社SmartHR
出典:SmartHR https://smarthr.jp/
無料プランあり
トライアルあり
IT導入補助��金対象
上場企業導入実績あり
株式会社SmartHRが提供するSmartHRは、雇用手続きや労務管理をクラウドで効率化できる人事・労務プラットフォームです。医療・福祉業界での導入も進んでおり、職員情報の集約・最新化を通じて、ID管理の土台になる「正確な人事マスター」を整備できます。
SmartHRでは、職員情報を一元化し、各種システムと連携する前提のデータ基盤として使える点が強み。加えて、対応プランでは外部ID管理サービス(Sentry)との連携により、SAML/SCIMを活用したアカウント連動が可能です。
また、職員の基本情報、所属、雇用形態、在籍状況などを一元管理し、入職時の手続きや退職時の情報整理をオンラインで完結可能。人事労務の流れが整うことで、院内システムのアカウント発行・停止に必要な「正しい人事情報」を安定して供給しやすくなり、棚卸や権限見直しの前提づくりに貢献します。
主な機能
- 提出依頼の通知
- 導入支援・運用支援あり
- 導入支援・運用支援あり
- 導入支援・運用支援あり
GMOトラスト・ログイン
GMOグローバルサイン株式会社
出典:GMOトラスト・ログイン https://www.globalsign.co.jp/
GMOグローバルサイン株式会社が提供するGMOトラスト・ログインは、複数のクラウド/Webサービスへのシングルサインオン(SSO)とID・パスワードの一元管理を提供するIDaaSです。医療機関の多システム環境において、認証の統一とセキュリティ強化を実現可能なサービスです。
多数のSaaSやWebシステムを導入する医療現場に適しているのが特徴。複数サービスのログインをまとめ、現場の「ログインの手間」や「パスワード使い回し」リスクを抑えやすい点が魅力です。多要素認証にも対応し、院内外からの不正ログイン対策にも有効です。
また、
SSOによるログイン統合、ID/パスワードの集中管理、認証強化(多要素認証など)を行うことも可能。端末移動が多い外来・病棟でも認証をスムーズにしつつ、情報漏えいの温床になりやすい共用ID運用の抑止にもつながります。
SeciossLink
株式会社セシオス
出典:SeciossLink https://www.secioss.co.jp/pricing/
株式会社セシオスが提供するSeciossLinkは、クラウドサービスからオンプレミスまで幅広いシステムに対し、統合SSO環境と認証・アクセス管理を提供するIDaaSです。院内に残るレガシーシステムも含めて認証基盤を統合したい医療機関で採用されやすい製品です。
医療機関はオンプレとクラウドが混在しやすく、電子カルテや部門系システムの認証がバラバラになりがちです。SeciossLinkはSAMLやOpenID Connectなど複数方式で連携でき、院内の“現状システムを生かしたまま”SSOを構築しやすい点が特徴。アクセス制御やライフサイクルへの対応も視野に入れた統合型の設計です。
また、複数システムへのSSO、クラウド・オンプレ横断の認証統合、認証強化やアクセス制御を実現可能。医師の当直端末や病棟の共有端末など、利用場所や時間が変わる医療現場でも、統一された認証ルールで運用しやすくなります。
OpenStandia KAID
株式会社野村総合研究所
出典:OpenStandia KAID https://openstandia.jp/solution/openstandiakaid/
OpenStandia KAIDは、野村総合研究所(NRI)のOpenStandiaブランドが提供するID管理・IDガバナンス(IGA)サービスです。利用者IDの登録・変更・削除といったライフサイクルを統制し、適切な認証・認可を実現することを目的とした次世代型のIDaaSとして位置づけられています。
OpenStandia KAIDは、NRIが蓄積してきたID統制のノウハウをテンプレート化したガバナンス機能を備え、申請・承認ワークフローやロール/ポリシー設計を通じて、院内の権限管理を標準化しやすい点が特長。またSaaS型に加え、要件に応じた提供形態を選びやすく、既存の認証基盤と組み合わせて運用を強化できる柔軟性もあります。
また、病院職員や委託スタッフなどのIDを一元管理し、入職時のID発行、異動・昇進時の権限変更、退職時の削除を含むライフサイクル管理が可能。加えて、アクセス権の申請・承認フロー、ロールに基づく権限付与、定期的な棚卸(アクセス認定)、IDに関する監査証跡の記録・レポート出力などに対応しています。

ここからは、医療機関がID管理システムを導入した際にどのような効果が得られるのかを紹介します。日常的なアカウント管理業務からセキュリティ対策、監査対応まで、幅広い面で改善が期待されます。ぜひ、効果を具体的に思い描いた上で、システムの選定を行いましょう。
ID管理システムを導入すると、アカウント発行や棚卸し作業にかかる手間を大幅に減らせます。医療機関では、医師・看護師・技師・事務など多職種が在籍し、入退職や異動が頻繁に発生します。そのため手作業でのID管理は漏れが生じやすく、担当者の負荷も大きくなりがちです。
自動化機能を備えたシステムであれば、入職時の一括発行や異動時の権限変更をワークフローに沿って実行できます。定型作業を効率化することで、情報システム担当者はより重要な改善業務に時間を割ける点がメリットです。
ID管理システムは、不正アクセスや操作ミスによる情報漏えいリスクの低減に効果があります。手作業での権限設定は属人的になりやすく、必要以上の権限が付与される“過剰権限”が起きやすい点が課題です。システムを活用すると、職種や役割に応じた標準ロールを設定し、適切なアクセス権限を維持できます。
また、アクセス状況をリアルタイムで記録できるため、不審なログインや操作の早期発見にもつながります。国内の病院では、アクセス制御の可視化により誤操作のインシデント件数が減少した事例も報告されています。セキュリティの強化と同時に現場の安心感を高められる点が大きな利点です。
医療情報を扱う以上、監査証跡の保存やアクセス履歴の記録は欠かせません。ID管理システムを導入すると、誰がいつどのシステムにアクセスしたかを自動的に収集でき、法令やガイドラインに沿った形でログを保持できます。
特に、
医療情報システム安全管理ガイドラインでは、アクセス管理と監査の実施が求められており、手作業で対応するには限界があります。
システム化することで、監査時のログ抽出も迅速に行え、担当者が手作業で資料を集める必要がなくなります。実際、監査準備に数日かかっていた病院が、わずか数時間で対応できるようになった例もあります。コンプライアンス強化と業務効率化の両方を実現できる点が導入メリットです。
ID管理システムは、医療機関内のアカウント管理プロ�セスを標準化し、運用負荷の軽減に寄与します。従来は、部門ごとに異なる手順でアカウント発行を行っていたり、申し送りが口頭で行われたりするケースもあり、ミスや遅延の温床になっていました。
システムを導入すると、申請から承認、発行までの一連の流れが統一され、業務が可視化されます。これにより、新任担当者でも運用に参加しやすくなり、属人化の解消にも役立ちます。
さらに、多くのシステムでは権限やルールをテンプレート化できるため、院内全体で均一な品質の運用が可能になります。組織全体のIT管理レベルを底上げし、担当者の精神的負担も軽減できる点が評価されています。

医療く向けID管理システムは、受付から診療、外部連携まで幅広く利用でき、院内運用の質を高めてくれます。ここからは、ID管理システムが医療機関のどのような場面で活用されるのかを更に具体的に紹介していきます。
医療機関では、受付・検査・診療といった複数の工程でスタッフがシステムを切り替えて利用します。この流れの中でID管理システムを活用すると、必要なシステムへシームレスにログインでき、業務が滞りにくくなります。理由としては、認証情報が一元管理されるため、利用者ごとの権限やアクセス条件が明確になるためです。
例えば、大規模病院では受付端末と外来診察室の端末間でシングルサインオンを導入し、ログインの繰り返しを減らして待ち時間改善につなげた例があります。こうした運用が実現すると、スタッフの移動が多い外来でも業務効率を保ちやすくなります。結果として、認証連携運用は医療の現場をスムーズにする重要な活用シーンといえます。
電子カルテは医療機関の中核システムであり、ID管理システムと連携することで安全かつ効率的に運用できます。特に、医師・看護師・技師などの職種ごとに閲覧範囲が異なるため、権限設定が適切に行われていることが重要です。
ID管理システムを活用すると、役割に応じたロール設定を行い、過剰な権限を防ぎやすくなります。また、異動時の権限変更も迅速に行えるため、情報システム部門の負担が軽くなる点も利点です。このように、電子カルテとID管理の連携は、診療情報の安全性と運用効率の両立に直結します。
地域連携システムや検査会社、訪問看護ステーションなど外部機関とデータを交換する際にも、ID管理システムは有効に機能します。理由として、外部ユーザーのアクセス制御を院内の管理ルールに合わせて統一できるためです。
アクセスログを確実に残せるため、情報の扱いに透明性が生まれる点もメリット。さらに、外部委託企業が関与するケースでは、契約範囲に基づいた権限付与を自動化し、運用ミスを避けやすくなります。このように、外部との安全な連携を支える基盤として、ID管理システムは欠かせない役割を果たします。

ここからは、医療機関がID管理システムを導入する際に注目すべきポイントを紹介します。ぜひ参考にしてください。
電子カルテを含む院内システムとの連携性を確保できるか
ID管理システムを選定する際には、電子カルテや部門システムと円滑に連携できるかを優先して確認する必要があります。
医療機関では、外来・検査・放射線・薬剤部・手術部など多岐にわたるシステムが稼働しており、それぞれで認証方式やアクセス要件が異なることが少なくありません。連携性が不十分だと、複数のID・パスワード��管理が必要になり、スタッフの負担が増えるだけでなく、誤操作やセキュリティリスクにもつながります。
一方で、電子カルテを中心とした主要システムと統合できれば、認証作業の一元化が進み、ログイン手順の統一やアクセス権限の管理が容易になります。こうした環境は、医療の現場で求められる迅速さや正確性にも寄与します。結果として、院内システムとの連携性は、日常業務の効率と安全性を大きく左右する重要な選定基準となります。
医療機関では、医師・看護師・薬剤師・検査技師など多職種が関わり、さらにシフト制で勤務するケースも多くあるため、ID管理システムでが職種や業務内容に合わせて柔軟に権限設定できるかが非常に重要です。適切な権限管理が行えると、必要以上の情報にアクセスできない状態を保ち、過剰権限によるリスクも抑えられます。
実際に、ロールベースで権限を設計した医療機関では、誤閲覧や権限漏れが減り、セキュリティ向上につながった例があります。さらに、応援勤務や部署をまたぐ作業が発生した際にも、権限変更を迅速に行える点がメリットです。こうした柔軟性は、日々変動する医療現場に非常に適しています。
医療機関のID管理では、アカウントのライフサイクルを自動化できる仕組みが重要です。入退職や異動、研修医・非常勤・委託先の出入りなど人の動きが多く、手作業だと発行遅れや停止漏れが起きやすいためです。
人事マスタ等と連携し、着任日に自動でIDを発行し、部署替えに合わせて権限を更新、退職・契約終了と同時に即時無効化まで行えるかを確認しましょう。職種・役割別の権限テンプレート、期限付きアカウントの自動失効、例外権限の申請・承認、定期的な権限棚卸しまで一つの基盤で回せると、現場負荷を抑えつつ過剰権限やアクセス残存を防げます。
ID管理システムは、医療機関特有のセキュリティ要件と監査対応を満たせることが必須です。個人情報保護法や医療情報システム安全管理ガイドライン等に沿い、「誰が・いつ・何に・どの権限でアクセスしたか」を明確に示せる状態を常に維持する必要があるためです。
多要素認証やSSO、最小権限を支える権限テンプレート、権限変更の履歴と理由の記録、操作ログの改ざん防止・長期保管が備わっているかを確認しましょう。特権IDも利用前の承認、利用中のセッション記録、利用後の自動棚卸しまで一気通貫で監視できると安心です。監査レポートの自動生成や、部門分離・二重承認などのルールを柔軟に設定できる拡張性も重要なチェックポイントです。

医療機関向けID管理システムの費用は、クラウド/オンプレの形態、利用ユーザー数、連携対象システム数、求める認証や監査機能の範囲によって変わります。単純な相場比較だけでなく、自院の要件を整理したうえで、初期・運用・将来拡張まで含めた総額で捉えることが重要です。ここからは更に詳しく解説していきます。
初期費用と月額料金は、システムの導入形態と利用範囲を明確にした上で見積もることが大切です。医療機関では職種が多く、電子カルテやPACS、院内VPNなど複数システムと連携するため、一般的な価格表だけでは実態に合わないことがあるためです。
相場感としてはクラウド型の場合、初期費用は0〜4万円程度、月額は1ユーザーあたり300〜1,500円程度がよく見られるレンジです。例えば、クラウド型は初期投資を抑えやすい一方、ユーザー数課金や認証オプション(SSO/MFA等)に応じて月額が増減します。
オンプレ型はサーバーや構築費が初期に乗りやすい反面、運用コストは読みやすい傾向があります。 連携対象が増えるほど設計・設定費も増えるため、方式×規模×連携数で費用を分解し、自院に必要な範囲の目安を握りましょう。
ID管理システムは導入後に長く使うため、保守と機能追加の費用条件を最初に明確にしておく必要があります。制度改訂や院内システムの更改が起きやすい医療機関では、後から連携先や監査機能が増えることが多く、追加費用が不透明だと総額が膨らみやすいからです。
例えば定期アップデートや小規模な設定変更が保守範囲に含まれるのか、連携先追加、権限設計変更、監査レポート拡張が別途費用にな�るのかで負担は変わります。MFAや特権ID管理、ログ保管期間の延長、API連携などは課金対象になりやすい領域です。サポート時間やSLAと費用のバランスも含め、将来の運用像に照らして保守範囲と追加条件を固めましょう。
費用の妥当性は、ROIと総保有コスト(TCO)の視点で判断するべきです。初期費用や月額だけで選ぶと、運用工数やセキュリティ事故の潜在コストを見落とし、結果として高コスト構造になる恐れがあるためです。
例えば入退職・異動時のID発行や停止が自動化されれば、情報システム部門の作業時間や夜間対応が減ります。権限棚卸しや監査レポートが自動化されれば、監査準備にかかる工数や外部監査費の一部削減も期待できます。さらに退職者アクセスの残存や過剰権限を減らすことで、漏えい・内部不正などの損失回避にもつながります。削減できる工数、避けられるリスク、将来の拡張費を並べ、3〜5年程度のTCOで比較すると納得感のある判断ができます。
まとめ|医療現場に最適なID管理システムでセキュリティと運用を強化
ID管理システムの導入は、医療安全、コンプライアンス、業務の効率化を同時に実現するための「土台」です。電子カルテ連携の確かさ、多職種・シフト対応の柔軟性、ライフサイクル自動化の深さ、セキュリティ標準への適合度を軸に選べば、導入効果を最大化できます。
まずは現状の発行リードタイム、放置アカウント数、棚卸し実施率を測定し、改善目標を数値で定めましょう。次に、重要システムを対象に小規模パイロットを実施し、成功パターンを全院へ展開してください。最適なパートナーと仕組みを整え、安全で生産的な医療現場を一緒に実現していきましょう。
運営に関するお問い合わせ、取材依頼などはお問い合わせページからお願いいたします。