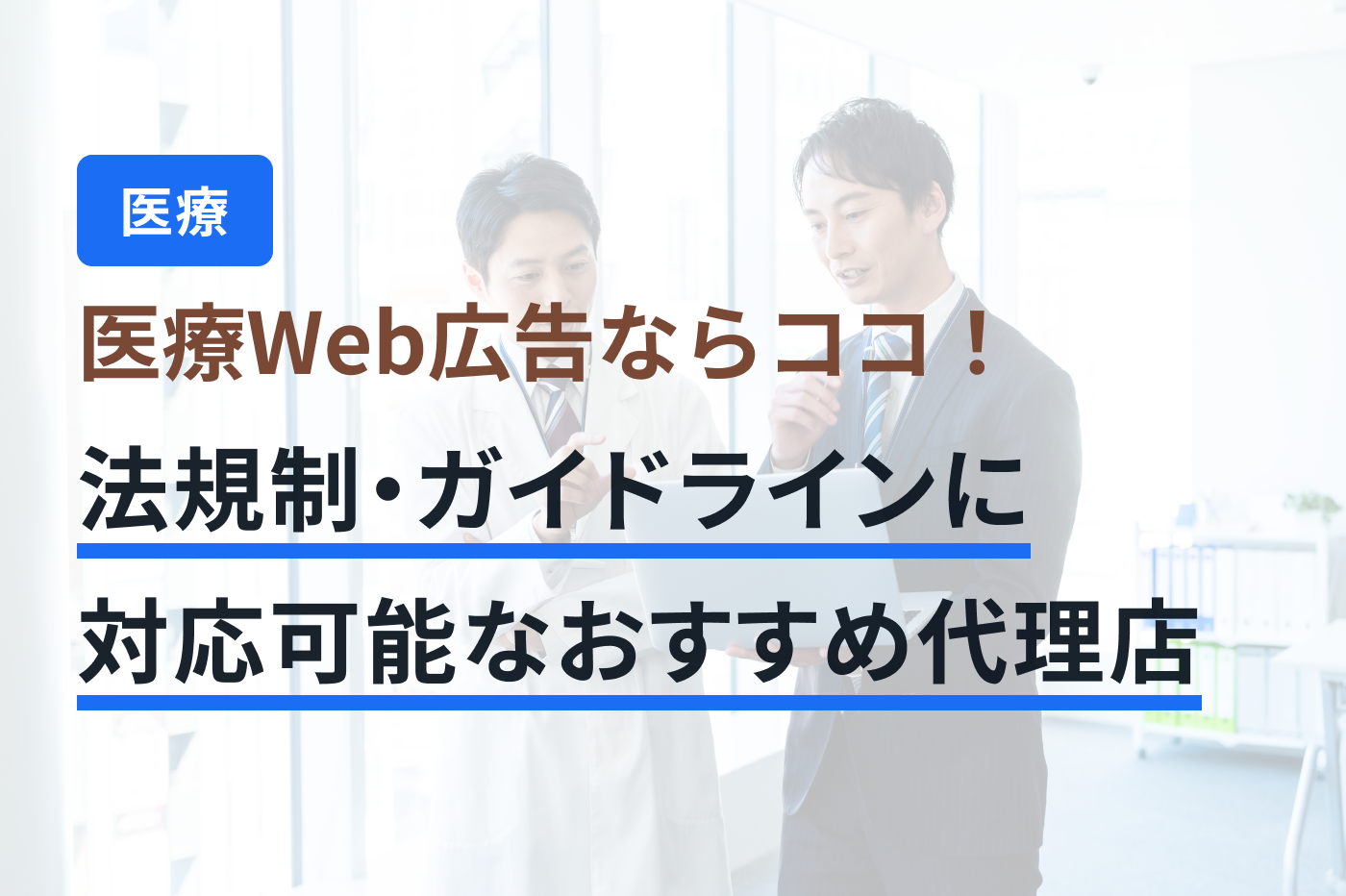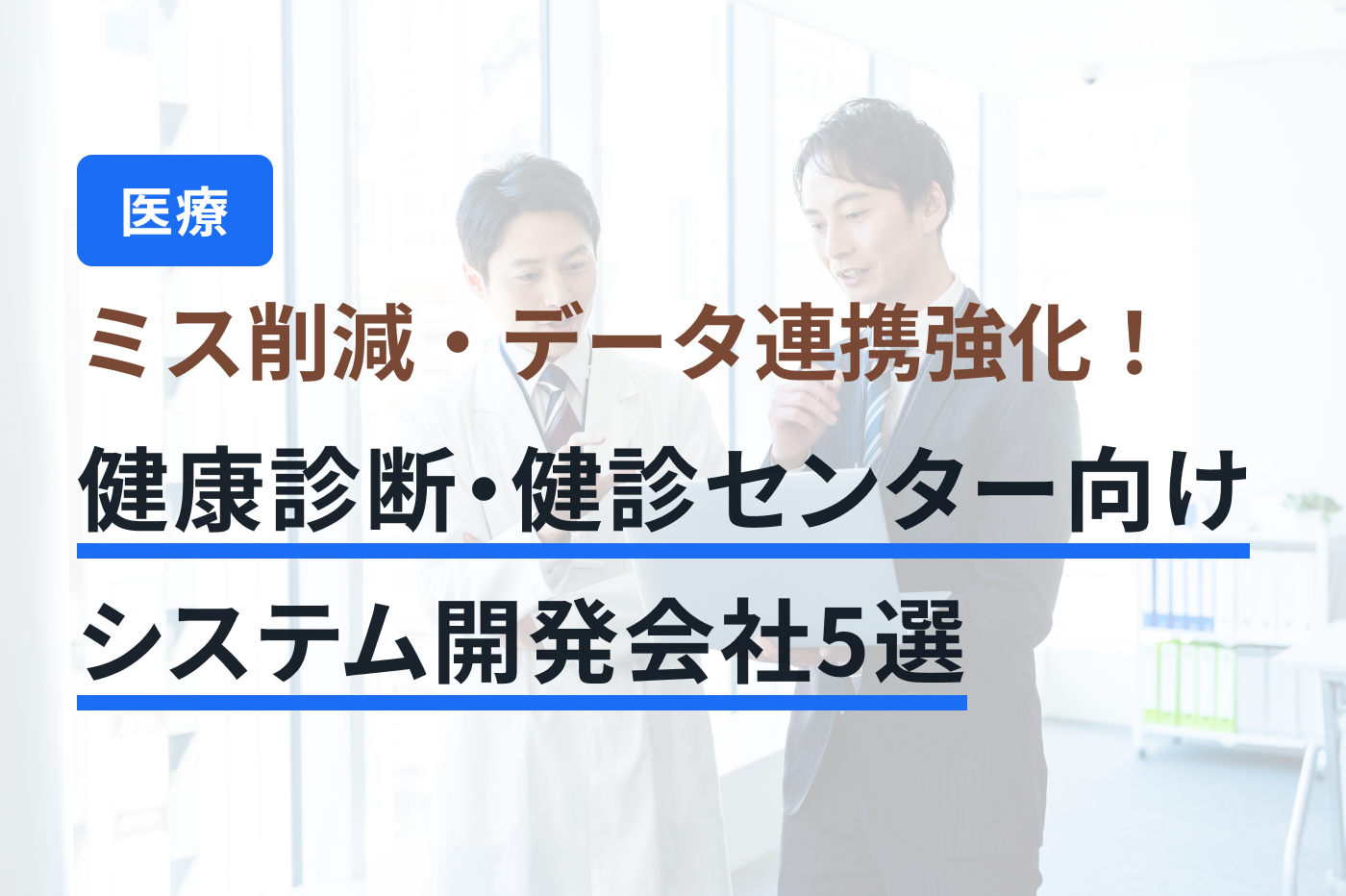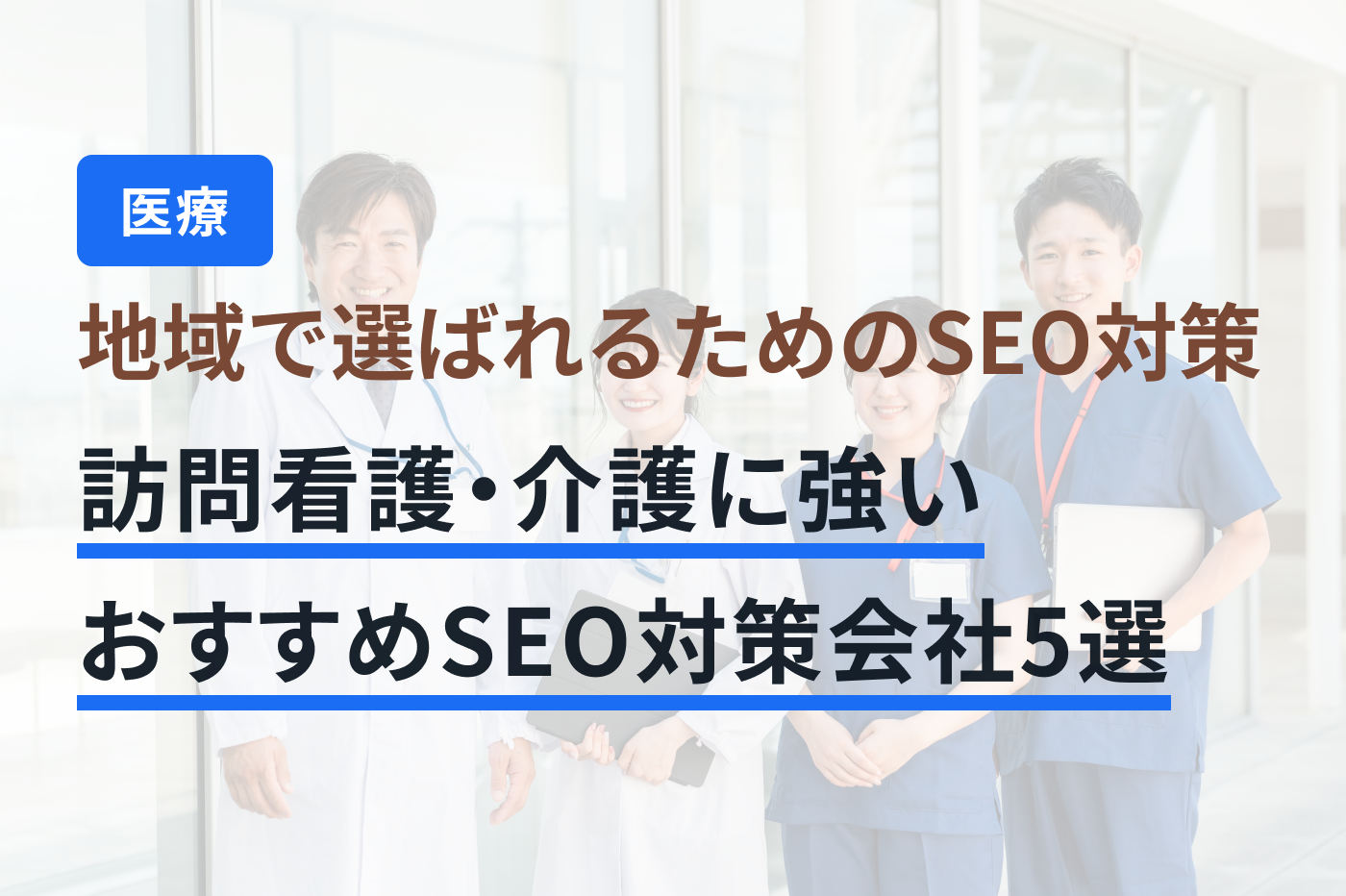医療機関向けおすすめWeb会議システム15選|導入のポイントと選び方ガイド
更新日 2025年11月14日
医療現場では、院内会議や症例カンファレンス、地域連携など、オンラインでのコミュニケーションが急速に広がっています。感染症対策の観点だけでなく、勤務形態の多様化や在宅医療の拡大もあり、Web会議システムの活用はもはや一時的な措置ではなく、医療体制の一部として定着しつつあります。
しかし、医療機関での導入には「個人情報の安全性」「医用画像の共有」「操作のしやすさ」など、一般企業とは異なる要件があり、どのツールが自社にあっているか判断できない人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、医療現場で実績があるおすすめのWeb会議システムをご紹介します。医療機関がWeb会議システムを導入する際の選び方と注意点も解説しているので、自院にあったツール選びの参考にしてください。
ここからは、医療機関向けにおすすめのWeb会議システムを厳選しご紹介します。
Zoom Meetings
Zoom Video Communications, Inc.
出典:Zoom Meetings https://explore.zoom.us/ja/products/meetings/
Zoom Meetingsは、Zoom Video Communications社が提供するクラウド型Web会議プラットフォームです。医療機関向けプランでは、遠隔診療・院内医師会議・地域医療連携・医療従事者教育��といった医療特有のニーズに対応する機能と認証を備えています。HIPAA(米国の医療情報保護規制)準拠環境や、医療機関専用の展開・運用ガイドラインが提供されており、安心して導入できる設計です。
医療ワークフローに沿った機能連携と使いやすさが特徴のほか、待機室機能やパスコード制限、ミーティングロック、暗号化、レコーディング管理など、患者との遠隔診療に求められるセキュリティ設定が充実しています。
さらには、多地点同時接続・スマートフォン・タブレット対応と、医師・看護師・遠隔拠点含めた参加が容易な点もポイント。医療機関が求める「セキュリティ」「連携」「実用性」をバランスよく備えたWeb会議システムとして人気があります。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- チャットサポートあり
- メールサポートあり
- 電話サポートあり
V-CUBE ミーティング
株式会社ブイキューブ
出典:V-CUBE ミーティング https://jp.vcube.com/service/meeting
V-CUBEミーティングは、株式会社ブイキューブが提供する国産のWeb会議システム。医療機関・自治体・研究機関など、高度なセキュリティを求める組織で広く採用されています。医療情報ガイドラインに準拠しており、院内LAN環境や閉域網での利用にも対応する安全性の高さが特徴です。
V-CUBEミーティングの強みは、医療現場に求められる高い映像・音声品質と、データ保護を両立している点です。通信が不安定な環境でも音声途切れが少なく、遠隔カンファレンスや診療連携会議でも安定した運用が可能。さらに、アクセス制限や多段階認証にも対応しており、外部からの不正アクセスを防ぎます。
また、録画・録音・チャットログを含む記録機能を活用することも可能。医療機関の情報管理ポリシーに準拠したWeb会議を実現したい施設に最適なシステムです。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- チャットサポートあり
- メールサポートあり
- 電話サポートあり
Microsoft Teams
日本マイクロソフト株式会社
出典:Microsoft Teams https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
Microsoft Teamsは、日本マイクロソフト株式会社が提供する統合型コミュニケーションツールです。チャットやビデオ会議、ファイル共有を一元管理できる点が特徴で、医療機関でも電子カルテやOffice製品との連携が容易です。
Teamsの特徴は、Microsoft 365との連携により、院内の文書管理や会議資料の共同編集がスムーズに行える点。医療情報を扱う際にもアクセス権限設定や多要素認証が可能�で、セキュリティ基準を満たした運用が実現します。
医療現場では、カンファレンスの開催、院内報告会、地域医療連携会議などに活用可能です。また、シフト調整や院内メッセージの共有など、日常業務のコミュニケーション効率化にも役立ちます。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- チャットサポートあり
- メールサポートあり
- 電話サポートあり
Cisco Webex Meetings
シスコシステムズ合同会社
出典:Cisco Webex Meetings https://www.webex.com/ja/video-conferencing.html
Cisco Webex Meetingsは、シスコシステムズ合同会社が提供する高信頼のWeb会議システムです。医療業界でも利用実績が多く、国際的なセキュリティ基準を満たしている点が評価されています。
特徴は、通信品質の高さと堅牢な暗号化技術です。多拠点を結ぶオンラインカンファレンスや医療従事者向けの講演会など、大人数でも安定した通信が可能。HIPAA(医療情報保護法)対応オプションもあり、医療データの安全な共有をサポートします。
医療機関では、手術症例の共有、遠隔地の専門医との意見交換、研修会や学会配信などに活用できます。リアルタイムで高解像度映像を共有できるため、教育・連携・研究のあらゆる場面で効果を発揮します。
主な機能
- チャットサポートあり
- メールサポートあり
- 電話サポートあり
- クラウド(SaaS)
Google Meet
グーグル合同会社
出典:Google Meet https://workspace.google.co.jp/intl/ja/products/meet/
Google Meetは、グーグル合同会社が提供するWeb会議システムで、Google Workspaceに含まれる信頼性の高いツールです。ブラウザベースで利用でき、医療現場でもスムーズに導入できます。
特徴は、簡単な操作性と自動文字起こし・翻訳機能。医療従事者の多国籍チームや海外学会とのやり取りにも対応し、国際医療機関や製薬企業の現場でも利用されています。
医療分野では、オンライン診療のバックヤード会議やチームカンファレンス、教育セミナーなどに活用可能です。Google Driveやスプレッドシートとの連携により、症例情報や研究データの共有も効率的に行えます。
主な機能
- チャットサポートあり
- メールサポートあり
- 電話サポート��あり
- クラウド(SaaS)
ISL Online
株式会社オーシャンブリッジ
出典:ISL Online https://www.islonline.jp/
ISL Onlineは、株式会社オーシャンブリッジが提供するWeb会議・リモートサポートツールです。1ライセンスから利用可能で、医療機関の規模を問わず導入しやすい点が魅力です。
特徴は、インストール不要で利用できる簡便性と、高度なリモート操作機能。サーバー構築が不要なクラウド型のため、IT担当者の負担を軽減しながら医療従事者がすぐに利用を開始できます。
医療現場では、遠隔地のシステム保守や、医療機器メーカーとの技術サポート、カンファレンス支援などに活用可能です。院内IT環境の運用負担を軽減しつつ、安全なリモート環境を実現します。
主な機能
- メールサポートあり
- オンプレミス(パッケージ)
- クラウド(SaaS)
- スマホアプリ(iOS)対応
LiveOn
ジャパンメディアシステム株式会社
出典:LiveOn https://www.liveon.ne.jp/
LiveOnは、ジャパンメディアシステム株式会社が提供する日本生まれのWeb会議システムです。医療機関や自治体など公共性の高い組織への導入実績が豊富で、セキュリティ面で高く評価されています。
特徴は、高音質・高画質で安定した通信が可能な点と、国内サーバ��ー運用による安全性です。音声がクリアで途切れにくく、医師・看護師・多職種チームの会話を正確に伝達できます。
医療・福祉現場のニーズに応え、スマートグラス連携(ハンズフリー操作)や院外/在宅との遠隔連携機能を備えているのも特徴。操作がシンプルで、ITに不慣れな医療事務スタッフや多職種の皆様でも使いやすく設計されており、導入・定着しやすい環境を構築できます。
主な機能
- メールサポートあり
- 電話サポートあり
- オンプレミス(パッケージ)
- クラウド(SaaS)
SaasBoard
ニューロネット株式会社
出典:SaasBoard https://saasboard.biz/
SaasBoardは、ニューロネット株式会社が提供するWeb会議システムです。クラウド型で、世界中どこからでも利用可能な拡張性の高さがあります。
特徴は、シンプルな操作性と安定した映像品質。ユーザー管理やアクセス制御の柔軟さも強みです。医療機関における多職種連携や外部専門医とのコミュニケーションにも適しています。
また、高画質・高音質の通信性能と、オンプレミス型の提供により院内ネットワークだけで運用可能。医療機関では、インターネット接続に制限を設けているケースも多く、外部接続を介さずに会議を実施できる点が安心とされています。また、ITに慣れていない医療従事者でも使いやすい操作性も導入決定の要因となっています。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- チャットサポートあり
- メールサポートあり
- 電話サポートあり
FreshVoice
エイネット株式会社
出典:FreshVoice https://www.freshvoice.net/product_list/freshvoice/
FreshVoiceは、エイネット株式会社が提供するWeb会議システムで、医療機関への導入実績が多い国産サービスです。クラウドとオンプレミスの両方に対応し、セキュリティ要件に合わせて選択できます。
特徴は、音声品質の高さと強固な暗号化機能。病院内の複数部門をつなぐ定例会議や、医療法人全体での経営会議などでも安定して利用できます。
また、院内LANに限定した閉域利用も可能で、外部接続を制限した安全な環境を構築できます。特に、個人情報保護が求められる大規模病院や大学病院におすすめです。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- チャットサポートあり
- メールサポートあり
- 電話サポートあり
sMeeting
NTTドコモソリューションズ株式会社
出典:sMeeting https://ddreams.docomo-sys.co.jp/smeeting/
sMeetingは、NTTドコモソリューションズ株式会社が提供するクラウド型のWeb会議システムです。NTTグループの通信技術をベースに開発されており、安定した通信環境と高いセキュリティ水準を両立しています。
PC・スマートフォン・タブレットなど、複数のデバイスから利用できる利便性と、社内外を問わず安全に接続できるアクセス制御機能が特徴。ドコモのネットワークを活かした堅牢な通信設計により、通信障害や品質低下が起きにくい構成を採用しています。
離れた拠点や在宅勤務者との情報共有が多い医療機関でも効果的な活用が可能。院内外のカンファレンスやチームミーティングを円滑に進めたい施設に適したシステムといえます。
主な機能
- メールサポートあり
- クラウド(SaaS)
- モバイルブラウザ(スマホブラウザ)対応
- 通信の暗号化
bellFace
ベルフェイス株式会社
出典:bellFace https://bell-face.com/
bellFaceは、ベルフェイス株式会社が提供するWeb商談・リモートコミュニケーションシステムです。インストール不要でブラウザから利用できる手軽さと、相手側への画面共有や資料提示をスムーズに行える操作性が特徴です。
主に営業や情報提供の場面で利用されており、医療関連企業でも遠隔で説明を行う際に最適です。録画機能やトークスクリプト表示機能を活用することで、説明内容のばらつきを抑え、情報提供の質を一定に保てる点が特徴です。
また、オンラインでの学術情報共有や、医療従事者向け説明会の実施を支援するツールとしても応用可能。幅広い業界で利用されている実績をもとに、安定した通信品質と使いやすい操作性を実現しています。こうした汎用性の高さが、医療関連企業にとっても安心して導入できる理由のひとつです。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- メールサポートあり
- 電話サポートあり
- クラウド(SaaS)
FACEHUB
FacePeer株式会社
出典:FACEHUB https://www.face-peer.com/service/index.html
FACEHUBは、FacePeer株式会社が提供するアカウント不要のWeb会議システムです。医療機関内での利用から、外部の家族・関係者とのオンライン面会まで幅広く対応可能です。
特徴は、ワンクリックで会議に参加できる簡便さと、利用者のIT知識を問わない直感的なUIです。高齢者施設や在宅医療現場など、操作に不慣れな利用者が多い環境にも適しています。
医療業界では、患者家族との面談、リモート診療サポート、地域包括ケアの連携会議などの活用に適しています。アカウント管理が不要なため、現場での負担が少なく、迅速に利用開始できます。
主な機能
- メールサポートあり
- クラウド(SaaS)
- スマホアプリ(iOS)対応
- スマホアプリ(Android)対応
MORA Video Conference
株式会社テリロジー
出典:MORA Video Conference https://www.web-kaigi.com/
MORA Video Conferenceは、株式会社テリロジーが提供する高セキュリティWeb会議システムです。オンプレミス環境にも対応しており、医療機関での安全運用が可能です。
特徴は、強固なセキュリティと多機能性。資料共有・録画・チャットなど、医療カンファレンスに必要な機能を標準搭載しています。国内データセンター運用で、個人情報保護も万全です。
医療分野では、院内教育、手術症例検討、医療法人グループ間の会議などに適しています。特にセキュリティ要件の厳しい病院におすすめのシステムです。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- メールサポートあり
- 電話サポートあり
- オンプレミス(パッケージ)
B-Room
株式会社Bloom Act
出典:B-Room https://www.broom-online.jp/
B-Roomは、株式会社Bloom Actが提供するクラウド型Web会議システムです。インストール不要で、ブラウザからすぐに会議を開始できます。
特徴は、音声・映像の遅延が少ない安定した通信品質と、わかりやすいインターフェース。医療従事者が多忙な環境でもストレスなく利用できます。
医療業界では、遠隔会議や院内研修、看護師採用面接などでの活用がおすすめ。専用アカウント不要で、外部講師や他施設の医師もスムーズに参加できる柔軟性が魅力です。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- チャットサポートあり
- メールサポートあり
- 電話サポートあり
スグニー
アウトリーチソリューションズ株式会社
出典:スグニー https://sugnee.jp/
スグニーは、アウトリーチソリューションズ株式会社が提供するビデオ通話・情報共有システムです。簡単な操作で通話や掲示機能を利用できる設計が特徴です。
タブレットを使った「ワンタップ通話」機能と、自動スライドショーによる情報共有が可能。特に高齢者施設や訪問看護ステーションなど、現場スタッフが迅速に情報をやり取り�できるよう配慮されています。
医療・福祉現場では、離れた拠点との連携、緊急時の安否確認、患者家族とのオンライン面会などでの活用がおすすめ。機器操作に不慣れな方でも安心して利用できるシンプル設計が魅力です。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- メールサポートあり
- スマホアプリ(iOS)対応
- スマホアプリ(Android)対応
医療機関がWeb会議システムを導入すべき理由と背景

医療現場でWeb会議システムの導入が進む背景には、感染症対策や業務の効率化だけでなく、地域連携や医療DXの推進といった社会的な流れがあります。従来の対面会議では難しかった多拠点間の意思疎通が容易になり、医療の質を維持しながら迅速な情報共有を実現できる点が大きな魅力です。
ここからは、導入が求められる具体的な理由を3つの視点から解説します。
近年、地域医療連携が進む中で、医療機関間の協力体制がより密接に求められています。大学病院や基幹病院が中心となり、地域の診療所や介護施設と連携して患者情報を�共有するケースが増加しています。こうした環境では、遠隔で専門医の意見を得たり、複数施設が同時に症例を検討したりする場面が増え、Web会議システムが欠かせません。
たとえば、がん診療連携拠点病院では、他施設との合同カンファレンスをオンラインで定期開催することで、移動時間の削減と診療の迅速化を実現しています。また、災害医療体制の整備にもWeb会議が活用され、現場との情報連絡を即時に行えるようになりました。このように、地理的制約を超えたリアルタイムの情報共有が、医療連携の質を高める基盤となっています。
新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、医療機関では対面接触を最小限に抑える仕組みづくりが求められました。院内会議や症例検討、さらには患者家族との面会までもが制限される中、Web会議システムは安全かつ効率的な代替手段として注目されました。
たとえば、集中治療室(ICU)では、患者家族が病棟に入れない状況下でオンライン面会を実施し、家族の心理的負担を軽減した事例があります。医師同士の情報共有でも、感染リスクを抑えながら診療方針を迅速に決定できるようになり、業務継続性を支える重要なインフラとなりました。
今後も感染症流行や災害など、対面が制限される状況に備え、Web会議システムは医療現場の安全確保と医療提供体制の維持に欠かせないツールとして定着していくでしょう。
医療現場では、医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務職員など多職種が連携して診療を行っています。チーム医療が重視される昨今では、職種や部門を超えた情報共有をスムーズに行うことが、診療の質を左右します。Web会議システムは、こうした多職種間の協働を支援するツールとして、日常業務に深く組み込まれつつあります。
たとえば、病棟、外来、薬剤部が同時に参加するオンラインカンファレンスを定期化した病院では、患者情報の共有ミスが減少し、診療プロセスの改善にもつながったと報告されています。
また、勤務体制の多様化により、夜勤明けスタッフや在宅勤務者もオンラインで参加できるようになり、チーム医療の連携強化に寄与しています。Web会議の活用は、医療の安全性と業務効率の両立を可能にする有効な手段といえるでしょう。

医療機関がWeb会議システムを導入する際には、一般企業とは異なる基準での選定が求められます。扱う情報が極めて機密性の高い医療データであることや、既存の電子カルテ・医用画像システムとの連携、現場の多忙な勤務環境などが影響します。
ここからは、医療業界ならではの重要な選定ポイントを5つの観点から整理します。
医療機関では、診療録や検査データ、画像情報など、個人情報を超える機微なデータを日常的に扱います。そのため、Web会議システムを導入する際は、通信経路の暗号化(TLSやAESなど)や多要素認証、アクセスログ管理など、セキュリティ機能の充実度を優先して確認する必要があります。
特に懸念されるのが、海外サーバー経由でのデータ通信や、会議内容が第三者に傍受されるリスクです。国内サーバーを利用する国産サービスや、医療情報ガイドラインに準拠した製品であれば、法令対応面でも安心できます。たとえば、LiveOnやV-CUBEなどは国内医療機関で多数導入されており、セキュアな通信環境の実績があります。
Web会議システムは利便性だけでなく、「
医療情報システム安全管理指針(厚生労働省)」への対応状況も確認しておくと安心です。
電子カルテやPACS、既存システムとの連携と拡張性
医療現場では、Web会議システムが単独で動作するだけ�でなく、電子カルテ(EMR)や医用画像管理システム(PACS)とのスムーズな連携が求められます。たとえば、症例カンファレンスで画像を共有したり、オンライン診療時にカルテ情報を参照したりする場面で、システム間の連携が滞ると業務に支障をきたします。
近年では、API連携やクラウド連携機能を備えたシステムも増えており、電子カルテや予約システムと自動連携できる仕組みが整いつつあります。特に大学病院や地域中核病院では、複数システムを統合的に運用する「医療情報連携基盤」の中で、Web会議を組み込む事例が多く見られます。
導入時には、既存ベンダーとの互換性や拡張性を確認し、長期的にシステムを統合運用できるかを見極めることが重要です。
医療現場では、会議中に通信が途切れたり、映像が乱れたりすることが業務に大きく影響します。特に手術カンファレンスや学会発表、遠隔地の専門医とのコンサルテーションなど、情報の正確性とリアルタイム性が求められる場面では、安定した��通信品質が欠かせません。
安定性を確保するには、帯域制御機能(ネットワーク負荷を自動調整)や、障害時に自動復旧する冗長化構成を備えたサービスを選ぶのが理想的です。Cisco WebexやZoom(医療機関向け)などは、世界中の医療機関で実績があり、通信品質と信頼性で高い評価を得ています。
また、院内ネットワーク環境も品質に影響します。Wi-Fiの電波状況やVPN設定を事前に確認し、安定した会議運用を支えるインフラ整備を進めることが重要です。
医療従事者の多忙な環境に対応する操作性・導入負荷の軽さ
医療従事者は多忙であり、ITに不慣れな職員も少なくありません。Web会議システムは操作が直感的で、専門知識がなくてもすぐに使えることが求められます。シンプルな画面構成やワンクリック接続など、短時間で会議を開始できる設計が理想です。
導入時には、トレーニングやサポート体制の充実度も重要です。たとえば、初期設定やトラブル対応をオンラインで支援してくれるサービスや、管理者向けに運用ガイドを提供するベンダーを選ぶと、現場への定着が早まります。導入負荷を最小限に抑えることが、運用定着のカギです。
院内だけでなく患者・在宅・他施設ともつながる運用支援とサポート
医療機関がWeb会議システムを導入する目的は、院内会議だけではありません。患者とのオンライン面談、在宅医療支援、地域施設との合同会議など、院外との連携にも幅広く活用されます。外部参加者への接続方法がわかりやすく、セキュリティを確保しながら安全にアクセスできる仕組みが必要です。
たとえば、V-CUBEやZoom(医療機関向け)では、URLリンクを送るだけで参加できる機能があり、患者や外部医師が簡単に会議へ参加できます。さらに、医療機関特有のサポート体制(24時間対応・医療機関専用窓口など)を持つベンダーであれば、緊急時にも安心です。
運用開始後も、利用状況の分析やトラブル対応をサポートしてくれる仕組みがあると、長期的な安定運用につながります。継続的な伴走支援を提供するベンダーを選ぶことが理想です。
Web会議システム導入から運用までのステップと成功のポイント

医療機関でWeb会議システムを導入する際は、単にツールを選ぶだけでなく、導入準備、試験運用、定着化、改善の各段階をしっかり踏むことが重要です。適切なステップを踏むことで、現場の混乱を防ぎ、安全かつ効率的な活用が可能になります。
ここからは、導入から運用までの具体的な流れと成功のポイントを4つの段階に分けて解説します。
導入前の準備段階では、まず「誰が中心となって進めるか」を明確にすることが第一歩です。IT担当者だけでなく、医師・看護師・事務職員など現場の代表を交えたプロジェクトチームを編成すると、実際の運用を想定した意見を取り入れやすくなります。
同時に、院内ネットワーク環境の確認も欠かせません。会議室や病棟エリアで安定した通信が行えるか、VPN接続やWi-Fiの強度、セキュリティ設定を事前に点検する必要があります。特に医用画像を共有する場合は、大容量データの送受信に耐えうる回線帯域が必要です。
さらに、利用端末(PC・タブレット・スマートフォン)のOSやブラウザ互換性も確認しましょう。導入初期に環境整備を徹底しておくことで、運用後のトラブルを大幅に減らせます。
本格導入の前には、小規模な部署で「パイロット運用(試験導入)」を行うことが推奨されます。これは、実際の使用感やトラブル傾向を把握し、本格導入時の課題を洗い出す目的があります。
たとえば、大学病院では特定の診療科やカンファレンスで先行利用し、通信品質・画面共有の操作性・医療情報共有時の安全性を検証しています。こうした試験を通じて得られた課題を改善�すれば、全体展開がスムーズに進みます。
また、導入時には利用ルールを明文化しておくことが大切です。会議の録画可否、資料共有方法、参加者の認証方式などを明確にし、全職員へ周知します。さらに、操作研修や動画マニュアルを用意することで、ITに不慣れな職員でも安心して利用できる環境を整えられます。
システム導入後は、単に運用を始めるだけでなく、利用を「習慣化」させる仕組みづくりが求められます。最初は一部の部署での利用にとどまる場合でも、成功体験を共有することで、院内全体への利用拡大が期待できます。
たとえば、定期的に「オンラインカンファレンス活用事例共有会」を開くと、職員の理解が深まり、他部署も積極的に利用を始めるケースがあります。管理者は利用状況をモニタリングし、アクセス数や利用時間を分析して改善に役立てましょう。
トラブル対応も重要です。通信障害やログイン不具合などが発生した際に迅速に対応できるよう、ベンダーのサポート窓口や院内ヘルプデスクを整備しておくと安心です。安定したサポート体制があれば、現場の不安も軽減され、長期的な定着につながります。
定期的な評価と改善(参加者数/利用頻度/業務効率化効果)
導入から一定期間が経過したら、システムの効果を定量的かつ定性的に評価することが必要です。参加者数、会議頻度、トラブル発生件数、職員満足度などを指標として定期的に測定し、改善サイクルを回します。
評価の際には、単に利用回数を追うだけでなく、「業務効率がどれだけ向上したか」「医療連携が強化されたか」といった実質的な成果も確認しましょう。こうした効果をデータ化し、定期的に院内へ共有することで、導入の意義を再認識できます。ベンダーと連携して機能改善や操作性向上を進めることも、長期的な品質維持に役立ちます。

Web会議システムの導入では、ツールそのものの性能だけでなく、「医療機関ならではの運用課題」を見落とさないことが成功の鍵です。多忙な現場でスムーズに使える環境を整えるには、リスクを想定して対策を講じることが欠かせません。
ここでは、医療現場で起こりがちな4つの注意点と、その回避策を解説します。
「無料プラン=十分」と判断してしまう医療機関ならではの落とし穴
導入コストを抑えようとして、無料版や汎用ツールを利用するケースは少なくありません。しかし、医療機関においては、無料プランではセキュリティやサポート体制が不十分である場合が多い点に注意が必要です。通信データが国外サーバーに保存されたり、暗号化方式が限定的だったりすると、個人情報保護の観点から大きなリスクを伴います。
たとえば、一般向けの無料ツールを使って患者情報を共有した結果、誤送信やアクセス制御の不備で情報漏えいにつながった事例も報告されています。医療機関では、無料版ではなく有料版、または医療向けの専用ライセンスを選ぶべきです��。導入前に「医療情報ガイドライン適合」「国内データセンター運用」などの条件を確認し、安全な運用基盤を確保することが重要です。
医療現場では、複数拠点を結ぶ会議や医用画像の共有など、大容量データを扱う場面が多くあります。そのため、通信帯域が不足していると、映像の遅延や音声の途切れといった問題が発生しやすくなります。特に、Wi-Fi環境が十分でない施設や古いネットワーク機器を使用している場合は、システム導入前に改善が必要です。
回避策として、帯域保証型のインターネット回線やVPN接続の導入が効果的です。また、Web会議システムの設定で「解像度の自動調整」や「音声優先モード」を活用することで、通信状況に応じた品質維持が可能です。
ある地域中核病院では、カンファレンス中の通信不安定が課題でしたが、LAN再構築とクラウド型VPNの併用により大幅に改善されました。通信環境の整備は、導入初期段階で最も重要な投資の一つといえます。
医療情報漏えい・扱い方のルールが曖昧なままで運用を開始するリスク
Web会議の利便性が高まる一方で、運用ルールが整備されないまま利用が広がると、情報漏えいのリスクが増大します。特に、会議の録画データや共有ファイルの扱いを明確にしていない場合、意図せず外部へ情報が流出する恐れがあります。
この問題を防ぐには、まず「医療情報管理規程」に沿った運用ルールを策定することが基本です。録画データの保存期間・保存先・削除ルール、参加者の認証方法、退職者や外部委託者のアクセス権限などを事前に定めておくことが重要です。
さらに、利用者全員にセキュリティ教育を行い、操作ミスや不注意による情報漏えいを防ぎましょう。厚生労働省が公表する「医療情報システム安全管理指針」に準拠した管理体制を整えることが、安全な運用への第一歩となります。
利用者(医師・看護師など)の操作負荷が高く定着しないケースも
システムが高機能であっても、現場での操作が複雑だと利用が定着しません。医療従事者は日々多忙であり、「ログイン方法が複雑」「資料共有に手間がかかる」といった小さな不便が、継続利用の障壁となります。
この問題を回避するには、導入段階で現場の声を十分に取り入れることが大切です。操作テストを複数部署で実施し、UI(ユーザーインターフェース)の使いやすさを確認しましょう。導入後は、簡単な操作マニュアルやFAQを院内ポータルに掲載し、誰でも迷わず使える仕組みを整えると効果的です。さらに、定期的なフォローアップ研修を行うことで、利用率の維持とトラブル低減が期待できます。
まとめ|医療機関に適したWeb会議システム選びを進めよう
医療機関におけるWeb会議システムの導入は、業務効率化だけでなく、安全で持続的な医療提供を支える基盤づくりでもあります。セキュリティ、既存システムとの連携、通信の安定性、操作性といった要素を総合的に検討し、現場に無理なく定着する仕組みを構築することが大切です。
特に、医療情報の保護や多職種連携の円滑化は、患者の安全性と医療の質向上に直結します。導入にあたっては、機能や価格だけで判断せず、運用サポートや拡張性、将来的なアップデート体制まで含めて比較・検討しましょう。複数のサービスを試し、現場の声を反映させながら慎重に選定することで、長期的に信頼できるシステム導入が実現します。最適なWeb会議システムを選び、医療現場の連携力を高めていきましょう。
運営に関するお問い合わせ、取材依頼などはお問い合わせページからお願いいたします。