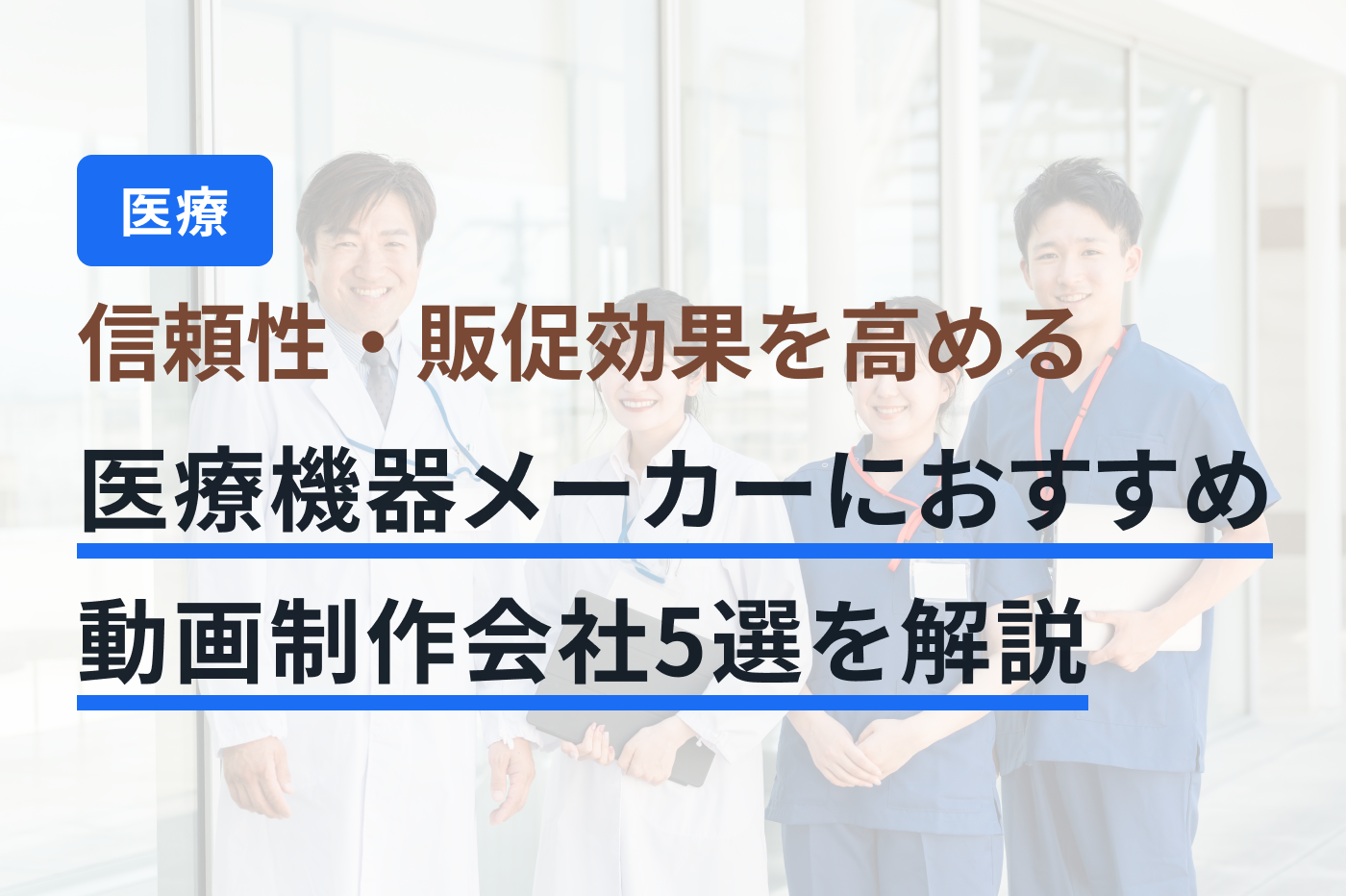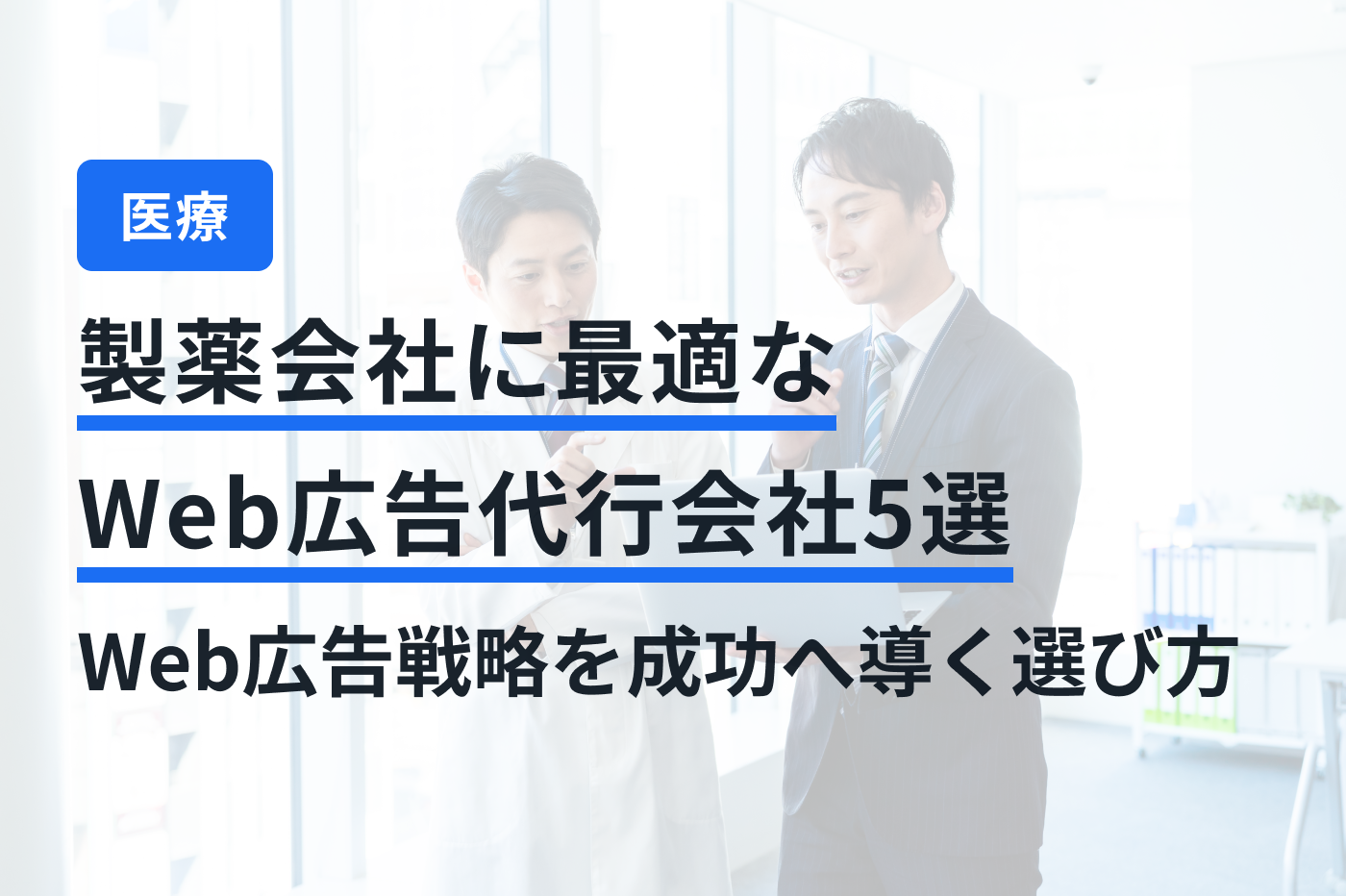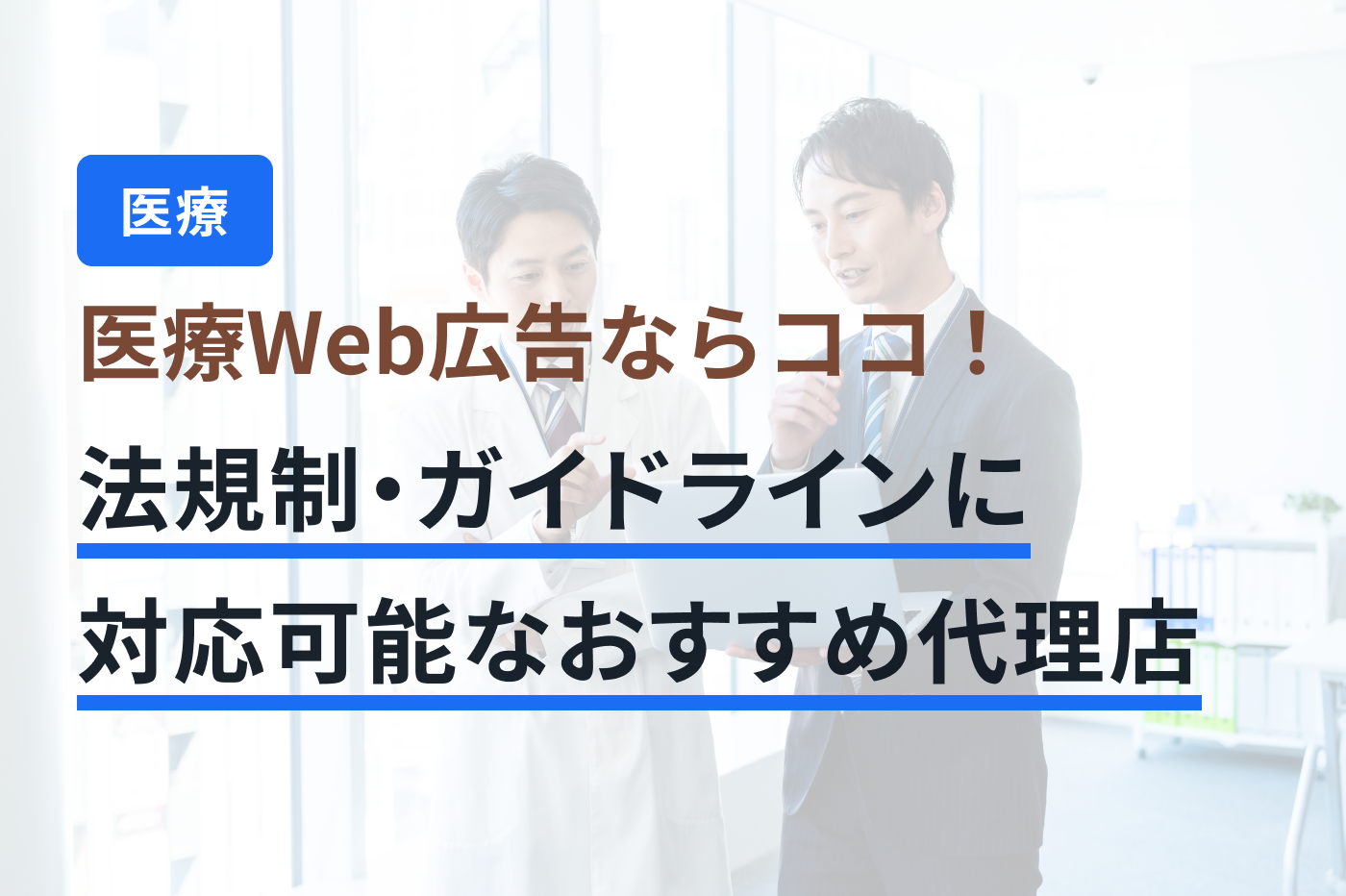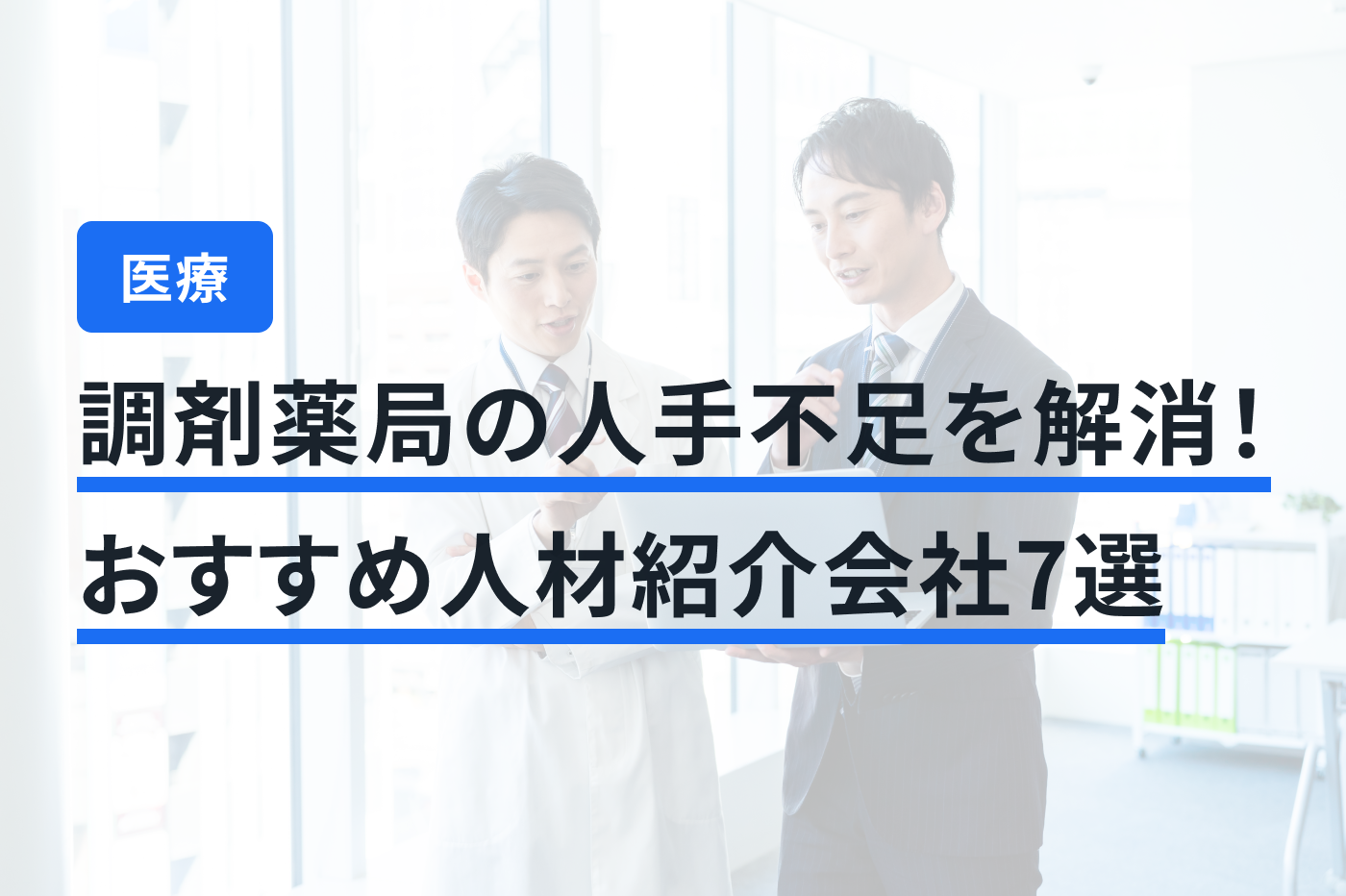医療機関向けにおすすめの契約書管理システム6選|選び方と導入ポイントを解説
更新日 2025年11月26日
医療機関では、診療委託契約や業務委託契約、個人情報保護に関わる同意書など、日々多くの契約書を扱います。しかし、紙で管理していると、「最新版が分からない」「更新期限を見逃す」「情報共有ができない」といったリスクが発生しやすいです。
契約書管理システムを活用すれば、医療機関の業務フローに合わせて契約書を一元管理でき、更新アラート、アクセス権限の細分化、電子契約との連携など、現場の負担を減らせます。
本記事では、医療業界におすすめの契約書管理システム6選を紹介します。導入��で失敗しないための選び方やチェックポイントを分かりやすく解説するので、自院に最適なツールを見つけ、リスクを抑えながら業務効率を高めたい方はぜひ参考にしてください。
まずは、医療機関におすすめの契約書管理システムをご紹介します。
クラウドサイン
弁護士ドットコム株式会社
出典:クラウドサイン https://www.cloudsign.jp/
無料プランあり
IT導入補助金対象
上場企業導入実績あり
クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービスで、医療法人・病院・クリニックなどでも広く導入されている電子契約システムです。日本法に準拠し、セキュリティ基準も厳格なため、医療機関で求められる高いコンプライアンス要件にも対応できます。
メールアドレスのみで契約手続きができるため、医療機関と取引先(医薬品卸・委託先施設など)の双方が導入しやすい点が強み。ISMSやSOC2など、医療データの取り扱いに適したセキュリティ基準もクリアしています。
また、クラウドサインでは、医薬品卸・委託検査会社・外部業者との契約を電子的に締結でき、契約書の検索や更新の自動通知も行えます。これにより、紙の契約書を保管する必要がなくなり、医療法人内の承認フローもオンライン化され、契約手続きが効率化されます。
主な機能
- 契約書のアクセスコード設定機能
- 本人確認書類による認証
- タイムスタンプ機能
- ワークフロー機能
クラウドリーガル
a23s株式会社
出典:クラウドリーガル https://www.cloudlegal.ai/
a23s株式会社が提供するクラウドリーガルは、AIを活用した法務アウトソースサービスで、医療法人の法務業務を幅広くオンライン化できるリーガルテックサービスです。契約管理をはじめ、労務、薬機法チェック、規程整備など多岐にわたる法務支援をワンストップで提供しています。
医療業界に特化した薬機法対応や広告審査に対応できる点が大きな特徴。医師の採用契約や医療機器のリース契約、訪問看護や介護事業所との取引契約など、多様な医療関連契約書の作成とレビューにも対応しています。
クラウドリーガルを利用すると、医療業界向け特有の契約書や規程の整備を専門家に任せることができます。広告表現の薬機法チェックや、電子契約による締結と契約管理の一元化、さらに登記変更や商標管理など医療法人運営に関わるバックオフィス業務まで幅広く支援を受けられるのが強みです。
主な機能
- AIによる修正
- 自動レビュー機能
- 法務業務アウトソーシング
- 広告審査業務アウトソーシング
ContractS CLM
ContractS株式会社
出典:ContractS CLM https://www.contracts.co.jp/
ContractS株式会社が提供するContractS CLMは、契約書の作成から締結、管理までを一元化できる契約管理システムです。医療機関における複雑な契約業務を標準化し、コンプライアンスを維持しながら効率化を実現します。
医師の雇用契約、医療機器メーカーとの取引契約、委託検査の契約など多様な業務に対応でき、契約プロセス全体を可視化して管理工数を削減可能。院内ルールに沿った承認フローが設定できるため、医療法人特有の決裁体系にも柔軟に対応できます。
また、ContractS CLMでは、契約書の作成から締結までのプロセスを一元化し、契約内容や履歴、更新期限を確実に管理できます。監査対応に必要な証跡を残しながら業務を進めることができ、契約に関わる担当者間の情報共有もスムーズに進みます。
主な機能
- 契約書作成
- ダッシュボード
- 雛形(テンプレート)管理
- ワークフロー機能
BtoBプラットフォーム 請求書
株式会社インフォマート
出典:BtoBプラットフォーム 請求書 https://www.infomart.co.jp/seikyu/index.asp
株式会社インフォマートが提供するBtoBプラットフォーム 請求書は、医療機関が関係する業者や委託会社との請求業務を電子化し、経理業務を効率化するサービスです。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しており、病院の経理DXを推進します。
医薬品卸、委託清掃業者、検査会社など、病院に関わる多くの取引先とのやり取りを電子化できます。大量の紙請求書の管理負担を大幅に軽減できるほか、テレワーク環境での経理業務にも対応しやすいのが特徴です。
請求書の受取・発行・支払処理�までをオンラインで完結でき、データの電子保存によって法対応もスムーズに行えます。さらに、医療材料費や委託費の支払状況を正確に把握でき、会計システムとの連携によって月次処理のスピードも向上します。
主な機能
- 受領帳票の保存
- 仕訳入力・記帳
- 電話サポートあり
- JIIMA認証
LegalForceキャビネ
株式会社LegalOn Technologies
出典:LegalForceキャビネ https://legalforce-cloud.com/company
株式会社LegalOn Technologiesが提供するLegalForceキャビネは、AIによる契約書管理に特化したシステムです。医療法人が抱える多様な契約書の管理やリスク把握を効率化できます。
AIが契約書から自動的に管理台帳を作成し、医療機関�に多い外部委託契約や医師雇用契約、医療機器のリース契約などを漏れなく管理できます。更新期限の通知機能によりコンプライアンスリスクを低減できる点が大きな特徴です。
また、LegalForceキャビネでは、契約書の電子データ化から分類、検索までを効率的に行えます。特に、期限管理や監査向けの証跡整理が容易になり、院内の契約管理レベルを一段と高められます。
主な機能
- AIによる自動抽出
- 契約管理台帳への自動登録
- 管理台帳のダウンロード
- 契約書のバージョン管理
LAWGUE
FRAIM株式会社
出典:LAWGUE https://lawgue.com/
トライアルあり
IT導入補助金対象
上場企業導入実績あり
FRAIM株式会社が提供するLAWGUEは、AIによる文書作成・チェックを得意とする契約書管理システムです。医療機関が扱う契約書作成やレビュー業務を効率化できます。
AIが文章チェックを行い、医療機関で注意すべき契約条項のリスクや記載漏れを自動的に検出。過去の契約書を基にしたテンプレート化により、医師の採用契約や外部委託契約を効率的に作成できます。
また、LAWGUEでは、契約書の文章チェックやテンプレート作成、全文検索、バージョン管理までを一貫して行えます。これにより、契約書作成の属人化を防ぎながら、更新管理や状況把握をスムーズに進められます。
主な機能
- AIによる修正
- 雛形(テンプレート)管理
- AIによる検索補助
- 全文検索

医療機関にとって契約書管理システムは、法令遵守と業務効率を同時に高める手段です。
紙や共有フォルダ中心の運用では、所在不明や版ずれ、更新漏れが起こりやすく、監査や第三者評価の際に大きな負担となります。条文や承認の履歴が可視化され、検索や更新の作業が短時間で完結できるのが、契約書管理をシステム化するメリットです。
ここからは、更に詳しく医療機関における契約書管理システムの活用メリットを解説していきます。
医療機関が契約書管理システムを導入する利点は、法令遵守や守秘義務に関わるリスクを大��幅に低減できる点にあります。医療情報や個人情報を扱う施設では、契約書の扱いにも厳密な管理が求められますが、紙文書主体の運用では閲覧履歴が残らず、誰が確認したのか後から把握しづらい状況が起こりがちです。
システム化することで、部署ごとにアクセス権限を設定でき、閲覧や編集の記録も自動で残せます。たとえば、特定の委託契約について診療科だけが閲覧可能とする制御も可能です。こうした管理体制は、監査の場面でも説明しやすさにつながります。法令対応を強化しながら、院内全体のリスクマネジメントを高める基盤づくりに役立つでしょう。
医療法や第三者評価に対応した証跡・ログ管理の高度化
監査や第三者評価に対応するには、作成から締結、更新、廃止に至るまでの行為が客観的に追跡できることが重要です。システム上では、起案・回付・承認・版の確定・アクセス履歴といった操作が自動記録され、改ざんが困難な形で保持されます。病院機能評価や内部監査の際、該当契約の履歴を時系列で提示できれば、説明責任を短時間で果たせます。
例えば、医療機器の保守委託契約に関する監査で、過去3年分の更新履歴と承認者、添付された性能検収書の確認状況を、数クリックで抽出可能です。紙ファイルを探し回る時間が削減され、審査側の信頼も得やすくなります。結果的に、監査準備のコストと心理的負担が大幅に軽くなります。
電子化により、保管スペースと検索時間が同時に縮小します。契約名、相手先、金額、部門、期間、キーワードなどのメタデータで横断検索できるため、探す時間が大幅に短くなります。スキャンデータにOCRを適用し、紙契約も全文検索の対象にできれば、過去の特約条項をすぐに再利用できます。
例えば、購買部が診療材料の購入基本契約の特約を確認したい場面で、従来は担当者の記憶やキャビネットを頼りにしていたものが、数十秒で該当契約と関連書類がリスト化されます。結果として、意思決定のスピードが上がり、現場の待ち時間も短縮されます。
誰の承認待ちで止まっているのか、次に誰に回付されるのかが見えると、停滞の早期解消につながります。アカウント連携(SSOやID連携)まで整えると、人事異動があっても承認者の更新が自動反映され、滞留が起きにくくなります。
また、治験契約のように関係者が多い案件では、院長決裁の前に治験管理室、薬剤部、看護部、情報セキュリティ担当の順でレビューを設定し、金額やリスクに応じて分岐させることも可能です。
メールやチャットへの通知で関係者の対応を促し、期限超過が続けば上長へ自動エスカレーションすることも。これにより、決裁リードタイムの短縮と、責任の所在の明確化が両立します。
契約書の保管先が統一され、最新版が明示されると、誤った版の使用が防げます。版管理(どの版が�有効かの管理)とアーカイブルールがあることで、過去版の参照は残しつつ、日常運用では必ず最新が開く設計にできます。
例えば、清掃業務の委託契約を見直す際、施設管理部・総務・法務が同じ最新版を参照し、追加条項も同じテンプレートから作成可能です。過去版は自動で履歴に退避され、検索時に誤って編集されることがありません。

医療 契約書管理システムを選ぶ際は、日々の運用で効く機能を絞り込み、実際の画面と操作感まで確認することが要点です。機能名だけでは差が見えにくいため、ユースケースでの再現性を確かめると失敗しにくくなります。
組織のどこにどの契約があり、どの版が有効かを一目で把握できる機能は必須級です。メタデータ設計(契約種別、相手先、院内部門、金額、期間など)と版管理、チェックイン・チェックアウト、命名規則の自動化がそろうと運用が安定します。
例えば、設備保守契約の改定時に「前回の条件」と「今回の変更点」を即座に参照できれば、判断の精度が高まり、作業の手戻りも防止できます。また、院内の誰が閲覧したのかという履歴も残るため、情報管理の透明性が向上します。こうした基盤が整うことで、契約管理の属人化を避け、安全性と業務効率が両立する体制を維持できるでしょう。
医療機関では、契約承認の流れをシステムで可視化することが重要です。なぜなら、法務・総務に加えて診療科や薬剤部など複数部門が関与するため、紙の回覧では進捗が分かりにくく、どこで止まっているのか把握できないことが多いからです。
ワークフロー機能を活用すれば、承認ルートが明確になり、各ステップの状況をひと目で確認できます。さらに、役職や職種ごとに承認権限を設定できるため、院内規程に沿った運用も維持しやすくなります。
例えば、新規の委託契約で「診療科 → 総務 → 法務 → 院長決裁」といった承認順序をそのまま再現することが可能です。このように、シス��テムによる承認プロセスの管理は、透明性と効率を高め、医療機関が求める運用体制づくりに大きく貢献します。
更新漏れはコスト増やサービス停止につながるため、複数タイミングでの通知が欠かせません。満了日の90日前、60日前、30日前など段階通知や、担当者不在時の代替通知、ダッシュボードでの要対応案件一覧があると安心です。
例えば、医療機器の保守契約は年度末に満了が集中しがちです。担当者・部門長・購買部に順次通知し、見積取得や稟議起票の期限も合わせてリマインドすれば、交渉時間を十分に確保できます。更新判断の根拠も履歴に残り、監査対応が容易になります。
医療機関のガバナンスを支える権限設定とセキュリティ機能
患者情報を直接扱わない契約でも、相手先情報や価格条件は秘匿性が高い領域です。役割ベースのアクセス制御、IP制限、多要素認証、透かし表示、ダウンロード可否、印刷制御などの細やかな権限定義が求められます。
また、組織改編に強いグループ管理や、退職者のアクセス自動停止、監査ログの長期保管も重要。暗号化(保存と通信)やバックアップ、災害対策の体制が明確であることも確認しましょう。
全体として、見たい人がすぐ見られ、見せてはいけない人には見えない状態を作れるかが評価軸になります。織改編に強いグループ管理や、退職者のアクセス自動停止、監査ログの長期保管も重要です。
誰がいつ何をしたかが、後から確実に追跡できることも重要です。承認・差戻し・版確定・ダウンロード・共有リンク発行などのイベントが自動記録され、改ざん困難な形で保持される必要があります。
期間や案件で抽出し、CSVやPDFで出力できると監査��提出がスムーズです。タイムスタンプや改定履歴の比較表示、監査人アカウントでの参照限定モードが用意されていれば、第三者に対する説明が短時間で完了します。
業務効率を高めるためには、契約書管理システム単体ではなく、電子契約や院内の既存システムと連携できることが重要です。電子契約サービスとつながれば、契約締結から保管までの流れが一体化し、二重登録やファイル添付の手間を減らせます。
また、勤怠システムやアカウント管理システムとの連携により、アカウントの自動更新や職員異動時の権限変更もスムーズになります。医療機関では部門間のデータ共有が課題となるため、外部システム連携は業務全体の整合性を保つうえで大きな役割を果たします。
さらに、一度のログインで複数のシステムにアクセスできるシングルサインオンを導入すれば、複数システムへのログイン負担も軽減されます。連携機能が充実しているシステムほど、現場定着のスピードも早くなるでしょう。

比較の出発点は、自院の実務を再現できるかどうかです。カタログスペックよりも、ユースケースの再現性と運用定着のしやすさを重視すると失敗が少なくなります。医療 契約書管理システムを候補ごとに並べ、現場での動きを検証しましょう。
同じ医療業界で実績があるシステムを選ぶことは、導入後の運用ギャップを最小限に抑えるうえで非常に重要です。医療機関特有の契約は、承認ルートも添付書類も複雑になりやすい特徴があります。こうした契約に対して、どのようにシステムが活用されているかを具体例として確認できれば、自院の運用に適合するかを判断しやすくなります。
評価の段階�では、単に導入事例を聞くだけでなく、実際の画面を見ながら自院の契約フローに近い操作を試すのが効果的です。たとえば、治験契約の回付フローや医療機器保守契約の更新時手続きを再現し、想定した通りの操作で完結するかを確かめると、運用後のイメージが明確になります。医療業界でのユースケースが豊富なシステムほど、導入後の負担が少なく、現場への定着も進めやすくなるでしょう。
院内の承認フローにどれだけ柔軟に対応できるかは、システム選定の重要な基準です。医療機関では契約の種類や金額によって承認ルートが変わるため、分岐条件や例外処理を現行ルール通りに再現できることが大切です。ノーコードで金額・種別による自動分岐や、並行レビュー、代理承認、差戻し時の戻り先指定などを設定できれば、現場負担を抑えながら運用できます。
さらに、治験契約など関係者が多い契約では、途中参加者を承認ルートに追加できるかも使い勝手に影響します。将来的に院内規程が変わった際、管理者が自院で設定変更できる仕組みがあれば、改定時のコストや調整の手間も減ら�せます。
既存の電子カルテや院内システムと適切に連携できるかどうかは、契約書管理システムの運用効率に大きな影響を与えます。なぜなら、SSO(シングルサインオン)や人事マスタとの同期、購買・会計システムとの連携が実現すれば、二重入力が解消され、職員の事務負担を大幅に減らせるからです。
たとえば、人事マスタと連動して部署異動時に権限が自動更新されれば、管理者による手動設定の手間も削減できます。また、連携は最初から全方位的に行う必要はなく、まずはログイン統合など負荷の低い部分から始め、必要に応じて段階的に拡張する方が現場にも定着しやすい運用になります。
さらに、データフローを図示し、患者情報と契約情報の境界を明確にしておくと、情報混在のリスクを回避でき、セキュリティ面でも安心です。このように、無理のない範囲で連携を整備しながら拡張性を確保することが、医療機関にとって最適なシステム活用につながります。
医療機関で契約書管理システムを運用する際は、複数部門が迷わず使えるUIであることが欠かせません。総務や法務だけでなく、診療科・薬剤部・看護部など、ITリテラシーが異なる職種が日常的に利用するため、画面構成が複雑だと操作に時間がかかり、導入後の定着が進みにくくなります。
分かりやすいメニュー配置や直感的な検索機能が備わっていれば、初めて触れる職員でもすぐに目的の契約書へたどり着けます。負担の少ないUIは、結果として院内全体での利用率を高め、システムを安全かつ継続的に使える環境づくりに役立ちます。
医療機関が契約書管理システムを選ぶ際、セキュリティ体制を厳密に確認することが不可欠です。契約書には委託情報や設備情報など機微性の高いデータが含まれ、不正アクセスやインシデントは�院内外に大きな影響を及ぼすためです。
確認すべき点として、データセンターの所在地、暗号化方式、脆弱性対応のプロセス、稼働率(可用性)の水準、バックアップと災害対策などがあります。また、第三者認証(情報セキュリティ関連の国際規格)の取得状況や、外部監査報告の公開有無は信頼性を判断するうえで役立ちます。さらに、万一のインシデント時にどのような報告体制が整備されているかも重要です。
運用面では、ユーザーごとに権限を適切に絞り込み、最小権限の原則を実現できる設計であるかを必ず確認しましょう。こうした多面的な安全対策が、医療機関に求められるガバナンスの基準を満たす土台になります。
契約書管理システムを選ぶ際には、費用の透明性を正しく把握しましょう。医療機関は導入後の長期運用を前提にするため、初期投資だけでなく総保有コスト(TCO)を見誤ると予算管理に影響します。費用を構成する要素には、ユーザー課金、ストレージ容量、ワークフロー数、API連携の利用可否、電�子契約の送信回数などが挙げられます。
さらに、データ移行、紙文書の電子化、テンプレート整備、職員研修など、初期に発生する作業費用も見落とされがちです。加えて、解約時にデータエクスポートが可能か、その際の費用が明確かどうかも重要な検討ポイントです。更新条件や割引の適用タイミングも早めに確認しておくと、後から想定外のコストが発生するリスクを抑えられます。このように、費用構造を丁寧に分解して比較することで、納得感の高い選定が行えるでしょう。
導入時の注意点と医療機関における運用定着のポイント

システム選定と同じくらい、導入プロジェクトの設計が成果を左右します。現場の手間を増やさない工夫と、段階的な展開計画が成功の鍵です。
システムを円滑に導入するには、まず院内の現行ルールや承認フローを正確に棚卸しすることが欠かせません。棚卸しを行うことで、現行フローのどこに課題があるのか、どの部分をシステム化すれば改善につながるのかが明確になります。
たとえば、契約種別ごとに承認ルートが曖昧になっている場合、紙運用では表面化しなかった遅延要因が可視化されます。また、この段階で「今��後のルールとして統一すべき点」も整理しておくと、導入後の混乱を防げます。最初にフローを可視化しておくことで、システム設計時の判断がスムーズになり、定着しやすい運用を構築できます。
契約書管理システムを上手く定着させるには、関係部門との調整を早い段階で行うことが重要です。なぜなら、医療機関の契約管理は法務・総務だけでなく、診療科や看護部、薬剤部など多職種が関わるため、どこか一部が不便に感じると全体の運用が滞るからです。
導入前に各部門へヒアリングを行い、業務上の課題や希望する運用イメージをすり合わせておくと、システム設計が現場に適した内容になります。事前に合意形成を図っておくことで、導入後の「使いにくい」「手順が増えた」といった不満を防ぎやすくなります。複数部門の理解と協力が得られれば、院内全体で安定した運用が実現します。
システムを定着させるためには、丁寧な利用者研修と分かりやすいマニュアル整備が不可欠です。理由は、契約管理に関わる職種が多岐にわたり、ITリテラシーに差がある医療機関では、初期段階でつまずくと利用が広がらないためです。
研修では、基本操作だけでなく「なぜシステム化するのか」という目的も共有すると理解が深まり、現場での抵抗感が減ります。たとえば、契約更新通知が自動化される仕組みや、承認の流れが可視化されるメリットを示すと、便利さが実感しやすくなります。
さらに、簡潔なマニュアルや動画チュートリアルを用意しておくことで、新任職員への引き継ぎや復習が容易になります。研修とマニュアルが整っていれば、利用者が迷わず操作でき、システムの浸透スピードが向上します。
システム導入後は、運用を見直し続ける改善サイクルを�構築することが大切です。なぜなら、導入初期は想定していなかった課題が現場で発生することがあり、改善を後回しにすると使いにくさが固定化されてしまうからです。定期的に利用状況を確認し、承認遅延や検索しづらい契約書がないかをチェックすると、改善ポイントが明確になります。
たとえば、診療科から「検索項目を追加してほしい」という要望が出た場合、設定を調整するだけで業務が一気に効率化するケースもあります。また、規程改定や体制変更に合わせてワークフローを見直し、院内ルールとズレが生じないように保つことも重要です。改善サイクルが定着すれば、システムは長期的に運用しやすい形へ進化し、院内全体の生産性向上にもつながります。
まとめ|医療特有の契約管理に対応したシステム選定が重要
医療機関では、契約書の更新管理や証跡提示、複数部門にまたがる承認フローなど、一般企業にはない独自の要件が多く存在します。そのため、こうした特性にしっかり対応できる契約書管理システムを選ぶことが、日々の業務を安全かつ効率的に進めるうえで欠かせません。
紙文書が部門ごとに散在しやすい環境でも、一元管理や検索性の向�上によって作業の正確性が高まり、監査時の準備負担も軽減されます。また、柔軟なワークフロー設定や権限管理、電子契約との連携が整えば、職員一人ひとりの作業がスムーズになり、現場のストレスも小さくできます。
自院の運用と相性の良いシステムを選ぶことで、契約管理が「負担」ではなく「支える仕組み」へ変わっていきます。こうした変化は、最終的に医療提供の質や組織全体のガバナンス強化にもつながります。自院に合うシステムを選び、持続的に運用できる体制を構築しましょう。
運営に関するお問い合わせ、取材依頼などはお問い合わせページからお願いいたします。