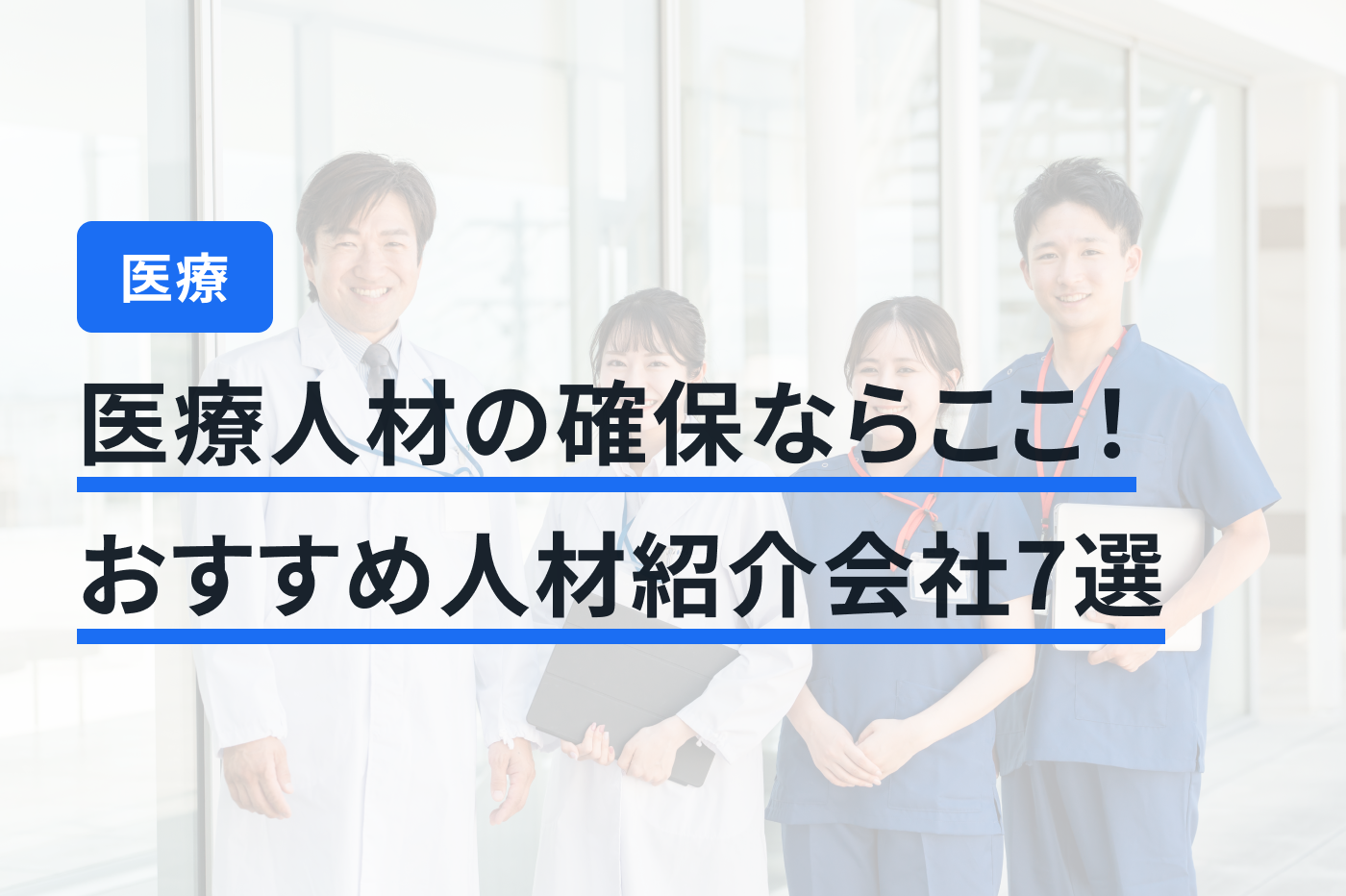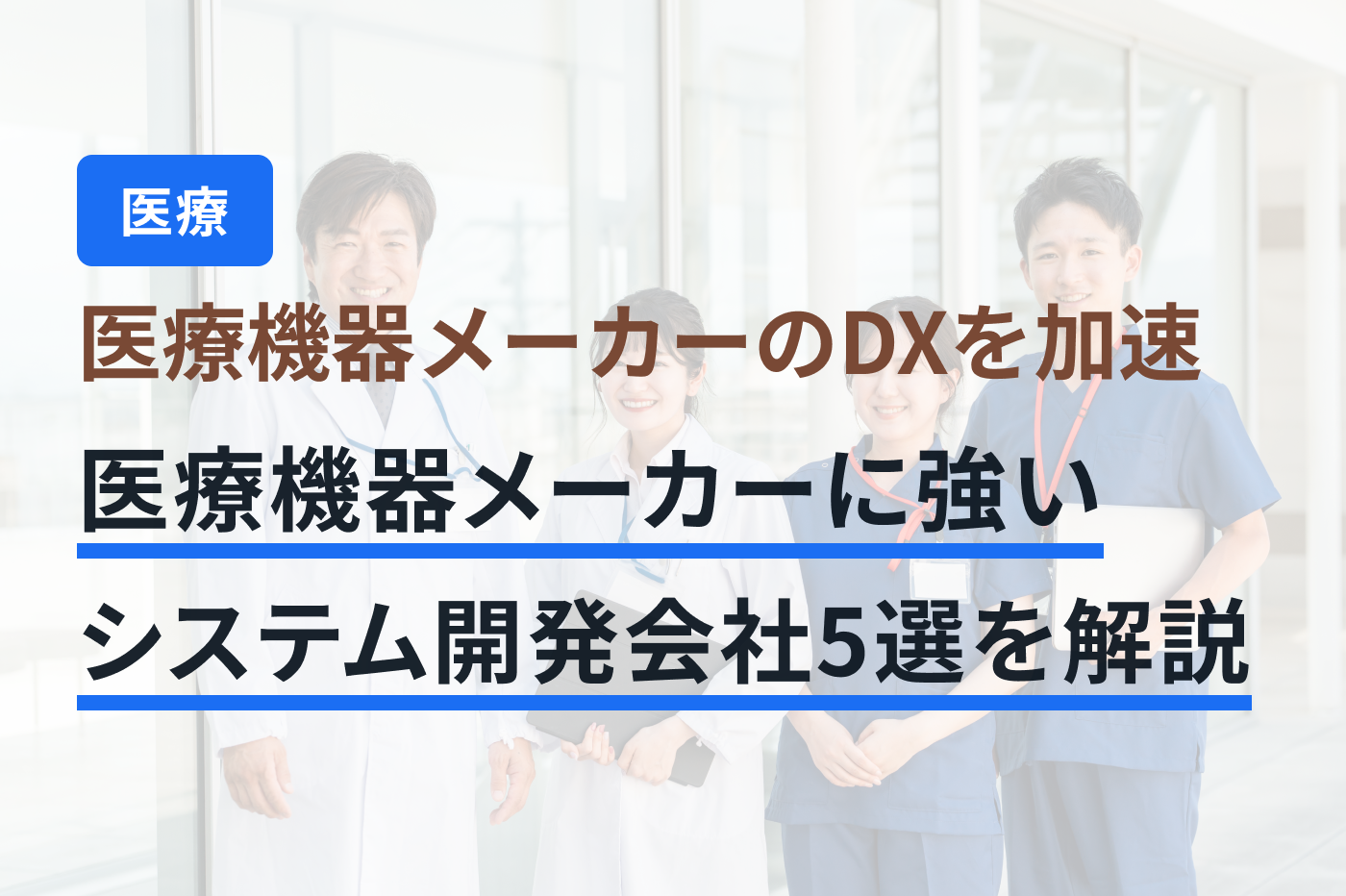医療機関に強いおすすめ会計ソフト7選|選び方と導入ポイントを解説
更新日 2025年11月18日
医療機関では、診療報酬の計上や補助金・委託費の管理、診療科別の収支把握など、一般企業とは異なる会計処理が求められます。そのため「通常の会計ソフトでは対応しづらい」「レセコンや電子カルテとの連携が必要」といった課題が生じることも少なくありません。
本記事では、医療機関に特化した機能を備えたおすすめの会計ソフトを紹介します。さらに、病院やクリニックが導入時に確認すべきポイントや、医療業界特有の会計処理における注意点も解説します。自院の会計業務に合った会計ソフト選びの参考にしてください。
ここからは、医療機関に特化した機能を備えたおすすめの会計ソフトをご紹介します。レセコン連携の強さや医療法人会計基準への対応状況、サポート品質など、医療機関ならではの視点で比較できるようにまとめました。ぜひ参考にしてください。
マネーフォワード クラウド会計
株式会社マネーフォワード
出典:マネーフォワード クラウド会計 https://biz.moneyforward.com/
トライアルあり
IT導入補助金対象
上場企業導入実績あり
マネーフォワード クラウド会計は、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型会計ソフトで、医療法人やクリニックでも広く採用されています。会計・勤怠・給与・経費などのバックオフィス機能を統合でき、医療現場の働き方に適した柔軟な運用が可能です。
勤怠データと給与・会計の連携に強みがあり、医師や看護師、医療技師など職種ごとに異なる勤務形態を自動で反映できます。シフトや手当の多い医療機関でも、入力作業の重複を避けながら正確に管理できる点が評価されています。
医療機関特有の夜勤や当直、オンコールといった勤務形態を正確に反映しながら勤怠を管理し、そのまま給与計算や会計処理へとスムーズにつなげられます。また、診療報酬や自費診療の入出金データとも連携し、医療法人会計基準に沿った自動仕訳が可能なため、バックオフィス全体の効率化に役立ちます。
主な機能
- メールサポートあり
- チャットサポートあり
- 電子帳簿保存法対応
- Mac対応
freee会計
freee株式会社
出典:freee会計 https://www.freee.co.jp/erp-professional.html?fr=top_lfo&set_ip2cinfo=true
トライアルあり
IT導入補助金対象
上場企業導入実績あり
freee会計は、freee株式会社が提供するクラウド型会計システムで、直感的な操作性と自動化機能が特徴です。医療機関でも導入が進んでおり、バックオフィスのIT化を低コストで始めやすい点が支持されています。
勤怠・給与・会計を一元管理でき、スタッフのシフト制勤務や変則勤務への対応力が高いのが特長。はじめて勤怠システ��ムを使うスタッフでも扱いやすいUIで、院内の負担を最小限にできます。
看護師・技師・受付スタッフなどの勤務時間を正確に管理し、そのデータを給与計算へ自動連携できます。さらに、医療法人に必要な帳票作成や、分院とのデータ共有にも利用できるため、医療機関全体の運営管理をスムーズに進められます。
主な機能
- 財務会計
- 電話サポートあり
- 電話サポートあり
- メールサポートあり
PCAクラウド会計
ピー・シー・エー株式会社
出典:PCAクラウド会計 https://pca.jp/
トライアルあり
IT導入補助金対象
上場企業導入実績あり
PCAクラウド会計は、ピー・シー・エー株式会社が提供する法人向けクラウド会計ソフトで、医療法人向けの機能が充実しています。信頼性の高いシステム基盤で、多院展開の医療法人からも選ばれています。
医療法人会計基準や部門別管理に対応し、医療機関の複雑な収支構造を正確に可視化できます。勤怠データとも連携しやすく、夜勤・当直の多い勤務体系でも精度の高い給与・会計処理が行えます。
診療科別の収支や部門別の損益を正確に分析しながら、医師や看護師の夜勤手当・当直手当を自動計算し、給与や会計へ反映。また、レセコンやカルテシステムとの連携により入力作業を最小限に抑え、医療機関の業務効率を総合的に改善します。
主な機能
- 電話サポートあり
- メールサポートあり
- 電子帳簿保存法対応
- 勘定科目のCSVインポート機能
FX4クラウド
株式会社TKC
出典:FX4クラウド https://www.tkc.jp/
FX4クラウドは、株式会社TKCが提供する会計システムで、会計事務所との連携に強い点が特徴です。医療法人会計に精通したTKC会員事務所のサポートが受けられるため、制度変更の多い医療業界でも安心して運用できます。
勤怠・給与・会計を一体で運用できるため、大規模病院や医療法人グループのようにスタッフ数の多い施設でもスムーズな管理が可能。経営管理の機能も充実しており、診療科別の収支や資金繰りを精緻に把握できます。
医師や看護師の複雑な勤務体系を勤怠データとして取り込み、そのまま給与計算や会計処理へ反映できます。さらに、診療科別の業績分析や金融機関向け資料の作成にも活用でき、医療経営の意思決定を支える仕組みを構築できます。
主な機能
- 電話�サポートあり
- 電子帳簿保存法対応
- Mac対応
- 取引明細の自動取込機能
Bill One請求書受領
Sansan株式会社
出典:Bill One請求書受領 https://bill-one.com/ap/
Bill Oneは、Sansan株式会社が提供する請求書受領システムで、医療機関に多い紙の請求書や複数部署での受領作業を効率化できます。
紙・PDF・メールなど形式の異なる請求書をオンラインで一元管理でき、医薬品・医療材料の仕入れが多い医療機関の負担を大幅に削減できます。部署ごとの承認フローにも対応し、病院特有の運用に合わせられる点も特徴です。
また、医療材料や医薬品の請求書をオンラインで集約し、部署ごとの承認フローに沿ってスムーズに処理できます。勤怠や会計システムへ自動連携できるため、病院全体のバックオフィス効率を高める基盤として活用できます。
主な機能
- メールサポートあり
- クラウド(SaaS)
- IP制限
- 二要素認証・二段階認証
大蔵大臣NX
応研株式会社
出典:大蔵大臣NX http://www.ohken.co.jp/index.html
大蔵大臣NXは、応研株式会社が提供する会計ソフトで、直感的な操作性と強固なセキュリティが特徴です。ITに不慣れな医療スタッフでも扱いやすい点が支持されています。
医療機関に必要な部門管理や手当計算に強く、夜勤・当直を含む複雑な勤務体系でも正確な処理が可能。アクセス権限管理にも優れており、個人情報を扱う医療機関でも安心して利用できます。
また、医療機関の職種別・部門別の勤怠データを正確に管理し、夜勤手当やオンコール手当を自動計算しながら給与・会計へ反映できます。医療法人決算に必要な帳票出力や、院内の情報管理を安全に行える環境が��整っている点も強みです。
主な機能
- 電話サポートあり
- メールサポートあり
- 電子帳簿保存法対応
- 勘定科目のCSVインポート機能
STRAVIS
株式会社電通総研
出典:STRAVIS https://www.isid.co.jp/
STRAVISは、電通総研が提供する連結会計・管理会計システムで、多院展開する医療法人やグループ医療機関での利用が広がっています。
複数拠点のデータを一元的に管理でき、勤怠・予算・経営データを横断して可視化できる点が特徴。医療法人グループ全体の財務や運営状況を俯瞰しやすく、経営管理の高度化を目指す場面で活用されています。
医療法人グループの連結決算や予算管理を一体で運用でき、各拠点の勤怠データも統合しながら、診療科別の収支や医療機器投資の判断材料となる財務データを精緻に管理できます。大規模医療法人の経営基盤を強化するための中核として機能します。
主な機能
- CSVインポート機能
- Excelインポート機能
- ファイルステータス確認
- 予算書作成

医療機関が会計ソフトを導入する利点は、医療ならではの複雑な会計業務を、正確かつ効率的に処理できる点にあります。診療報酬や自費診療の管理、法令に沿った財務処理、さらにはレセコンや電子カルテとのデータ連携など、会計以外の業務とも深く関わる領域が多く、手作業ではどうしても負担が大きくなりがちです。
会計ソフトを活用すれば、こうした業務の自動化やミス防止が可能となり、経営判断に必要なデータも蓄積しやすくなります。ここからは、医療機関が会計ソフトを導入することで得られる具体的なメリットを、収益管理・法令対応・データ連携などの観点から詳しくご紹介します。
診療報酬と自費診療の売上を自動で管理できることは、会計ソフト導入の大きな利点です。医療会計では、診療内容ごとに保険点数や算定ルールが異なるため、手作業で集計すると時間がかかり、計上漏れのリスクも避けにくくなります。
会計ソフトを使えば、レセプトデータや自費診療の売上情報が自動的に取り込まれ、保険診療と自費診療をまとめて正確に把握できます。実際に、美容医療を併設するクリニックでは、双方の売上推移をリアルタイムで確認できるようになり、広告費の配分やスタッフ配置の判断に活用されています。
自動化によって管理精度が高まることで、収益状況をより正確に把握でき、結果として経営判断の質も向上していくでしょう。
医療法人では、医療法で定められた会計基準に沿った財務処理が求められます。会計ソフトを導入すると、必要な勘定科目や決算書式に自動で対応できるため、法令準拠の負担を軽減できます。
また、税制改正の更新に対応しているソフトであれば、制度変更に気付かず誤った処理をしてしまうリスクも抑えられます。法令遵守が求められる医療機関にとって、正確な財務処理を支えるツールとして会計ソフトは重要な役割を担います。
レセコンや電子カルテとのデータ連携による手入力削減
レセコンや電子カルテと会計ソフトを連携させることで、入力作業を大幅に削減できる点は医療機関にとって大きなメリットです。医療現場では、診療内容や請求データが日々大量に発生し、これらを会計へ手作業で転記すると相応の時間がかかるうえ、入力ミスも避けにくくなります。
データ連携が可能なソフトであれば、診療報酬請求データや患者情報が自動で取り込まれ、入力の重複や確認作業を最小限に抑えられます。また、データの整合性が保たれるため、売上計上の精度が安定し、月次処理のスピードも向上します。
診療科ごとの利益・コストの「見える化」で経営判断の精��度を高められる
診療科や部門ごとの収支を分析できることは、医療機関の経営改善にとても有効です。医療法人では複数の診療科が存在し、それぞれで収益構造が異なるため、単純な全体損益だけでは実態をつかみにくい場面があります。
会計ソフトで部門別にデータを管理すると、どの診療科が安定して利益を生んでいるか、どの部門でコストが膨らんでいるかを明確に把握できます。適切なデータが蓄積されることで、経営判断がより実態に即したものになり、長期的な戦略にも活かしやすくなります。

ここからは、医療機関ならではの会計処理上の特徴をご紹介します。医療法人やクリニックでは、診療報酬請求の流れや助成金の取扱い、未収金管理など、一般企業とは異なる仕組みが数多く存在します。こうした特性を踏まえて会計処理を行うことが、適切な財務管理につながります。
医療機関では、診療報酬請求から入金まで約2ヵ月程度のタイムラグが発生します。月単位の収益と入金額が一致しないことが多く、資金繰りの管理が難しくなりがちです。
しかし、会計ソフトを活用することで、請求ベースと入金ベース双方で収益を把握でき、資金繰りの見通しが立てやすくなります。たとえば、入金予定を月別に一覧化できる機能を利用すれば、将来のキャッシュフロー不足に早期に気づけるようになります。診療報酬は医療機関にとって主要な収益源であるため、このタイムラグを的確に管理することが経営の安定に直結します。
医療機関では、自治体の補助金や国の助成金、委託費など、多様な財源を扱うことが少なくありません。これらは用途や会計処理のルールが異なるため、誤った科目で処理すると後の監査で問題になるケースもあります。
会計ソフトに医療特有の勘定科目が標準搭載されていれば、複雑な制度ごとの扱いを迷わず処理できます。たとえば、新規医療機器導入に伴う補助金の場合、収益計上のタイミングが厳密に決まっているため、ソフトのテンプレートが役立ちます。
制度の要件は変更されることも多いため、最新情報に対応した機能を備えるソフトを選ぶことが安心につながるでしょう。
医療法人や社会福祉法人は、独自の会計基準に基づいて財務処理を行う必要があります。一般企業向けの会計ソフトでは対応しきれない項目もあるため、基準に準拠した形式で決算書を出力できるソフトを選ぶことが重要です。
会計基準に沿��った処理が可能になると、監査対応もスムーズになり、提出書類の作成負担も軽減できます。たとえば、医療法人会計基準では、資金収支計算書をはじめとする特有の書式が求められますが、専用ソフトなら自動生成できます。会計基準への理解は専門性が高いため、ソフトが支援してくれることは大きな安心材料になります。
未収金や未払金が多く発生する医療機関特有の資金繰り対策
医療機関では、保険者からの入金遅延や患者負担分の未収金など、通常の事業より未収金が発生しやすい傾向があります。未収金が積み上がると資金繰りが悪化し、経営に影響する恐れもあります。
会計ソフトを活用すると、未収金の発生時期や回収状況を一覧で確認でき、滞留している項目の把握が容易になります。実際に、未収金管理の改善に取り組んだ医療法人では、回収フローの見直しとソフトの導入を組み合わせることで、回収率が前年より数ポイント向上した事例があります。資金繰りを安定させるためにも、未収・未払管理が強化できるソフトは有効です。
医療機関が扱うデータは、個人情報の中でも特に保護レベルの高い「要配慮個人情報」に該当します。会計ソフトを選ぶ際は、個人情報保護法や医療情報システム安全管理ガイドラインに沿ったセキュリティ対策が求められます。
通信の暗号化やアクセス権限の細分化、ログ管理などが備わっていれば、院内の情報漏洩リスクを大幅に下げられます。過去には、バックアップ管理が不十分だったことで会計データが消失し、決算作業に影響した事例もありました。高い安全性を確保しながら運用できるソフトを選ぶことが、医療機関にとっての大切な要件といえるでしょう。
医療機関の業務フローに適合した会計ソフトを選ぶためのポイント

ここからは、医療機関が会計ソフトを選定する際に特に確認したいポイントをご紹介します。レセコン連携の有無や会計基準への対応、安全性など、医療機関特有の要件を満たしているかを見極めることで、導入後の運用負担を大幅に減らせます。
レセコン(レセプトコンピューター)や電子カルテと自動連携できる会計ソフトは、医療現場の入力作業を大きく減らしてくれます。診療データの転記作業は手間がかかるうえ、誤入力のリスクも高まりますが、自動連携が可能であればデータの一致性を保ちながらスムーズに処理できます。
外来件数の多いクリニックでは、レセプト情報が自動で会計に反映されることで、月末作業が大幅に軽減された事例もあります。業務効率とミス防止の観点からも、医療機関には欠かせない機能といえます。
医療法人では、医療法人会計基準に沿った決算書類を作成する必要があります。一般的な会計ソフトでは対応していない場合もあるため、基準に準拠した書式を出力できるかは重要な判断基準です。
専用ソフトなら資金収支計算書や医療法人向けの貸借対照表を自動生成できることが多く、決算作業の負担を軽減できます。監査対応においても、基準に沿った帳票が整っていると指摘事項が少なく済むため安心です。制度変更にも適宜アップデートされるソフトを選ぶと、長期的な運用の安定につながります。
診療科別・部門別の損益管理が標準機能として備わっているか
診療科別や部門別の損益を把握できることは、医療機関の会計ソフト選びで欠かせない要素です。医療機関では診療科ごとに患者数や治療内容、材料費、スタッフ配置が大きく異なるため、全体損益だけでは経営の課題が見えにくくなります。
部門別管理が標準搭載されているソフトであれば、収益や費用を診療科単位で自動的に整理でき、どの部門が利益を生み、どこに改善余地があるのかが明確になります。たとえば、検査部門やリハビリ部門のように稼働率が業績に直結する領域では、日別・月別の利用状況と費用を照らし合わせることで、スタッフ配置や設備投資の判断に活かすことができます。
さらに、データが蓄積されれば、単月比較だけでなく前年同月比や季節変動の把握など、長期的な経営分析にも活用できます。これにより、不採算部門の早期把握や伸ばすべき部門への投資判断がしやすくなり、経営全体の方向性を検討する際にも役立ちます。
補助金や委託費、診療報酬の入金ズレなど、医療特有の勘定処理に正確に対応できるかどうかは、会計ソフト選びの重要な判断基準です。医療機関では、財源ごとに会計処理ルールが異なり、補助金には用途制限があったり、委託費には独自の報告様式が求められたりと、一般企業にはない複雑さがあります。
医療向けの会計ソフトであれば、補助金や委託費といった特有の勘定科目や、診療報酬の未収・入金ズレを前提とした処理機能があらかじめ備わっているため、制度に沿った正確な計上を支援してくれます。
また、更新性の高い制度に対応しやすい点もメリットで、補助金要件の変更や診療報酬改定があっても、ソフト側のアップデートにより適切な処理方法を維持できます。こうした医療特有の財源管理に強いソフトを選んでおくことで、日常の会計処理が安定し、財務データの信頼性も高まります。
会計事務所・税理士とのデータ共有がスムーズに行えるか
会計事務所や税理士とスムーズにデータ共有できるかどうかは、医療機関��が会計ソフトを選ぶ際に欠かせない視点です。医療機関では月次処理や決算業務を外部の専門家と連携して進めることが多く、データの受け渡しが煩雑だと作業全体の効率が落ちてしまいます。
クラウド型の会計ソフトには、閲覧権限を付与するだけでリアルタイム共有できるものも多く、双方で同じデータを見ながら処理を進められるため、確認作業の手間が軽減されます。
また、医療専門の税理士が特定の会計ソフトを推奨しているケースもあるため、既存の会計事務所との相性を事前に確認しておくと、導入後の運用がよりスムーズになります。共有形式やエクスポート機能が充実しているソフトであれば、月次データの送付や修正依頼といったやり取りも簡素化でき、コミュニケーションコストの削減にもつながります。
医療機関向けのサポート体制(制度改正や診療報酬改定への対応力)があるか
制度改正や診療報酬改定に確実に対応できるサポート体制が整っているかは、医療機関が会計ソフトを選ぶうえで重要な基準です。医療業界では算定ルールの変更が頻繁に行われるた�め、最新の制度に則って処理できる環境が欠かせません。
医療機関向けの会計ソフトには、専門スタッフが改定内容や設定方法を案内してくれるものや、アップデートにより自動的に新制度へ反映されるものもあり、担当者の負担軽減に役立ちます。
また、改定時は業務が煩雑になりやすいため、問い合わせへの迅速な対応や、変更点を整理したガイド資料が提供されるかどうかも重要。こうした支援体制が整っているソフトを選んでおけば、制度変更に伴うミスを防ぎながら、日常の会計業務も安定して進められるでしょう。
ここからは、医療機関向け会計ソフトの費用感についてご紹介します。クリニック向けのクラウド型から、医療法人向けのオンプレミス型まで、料金体系はソフトによって大きく異なります。自院の規模や必要機能に応じた費用を把握することが、無理のない導入につながります。
クラウド型の会計ソフトは、導入しやすい価格帯が特徴で、小規模クリニックや個人開業医に向いています。一般的には月額5,000~1万5,000円程度で利用でき、初期費用がゼロまたは低額に設定されている場合が多いです。
サーバー管理が不要なため、IT管理の負担も抑えられます。利用ユーザー数に応じて追加料金が発生するケースもありますが、必要最低限の機能から始められる点が魅力です。外来件数が安定しているクリニックでは、クラウド型で十分なケースが多く、コストパフォーマンスの高さから選ばれています。
中規模以上の医療法人や病院では、オンプレミス型の会計ソフトが選ばれることがあります。専用サーバーを院内に設置するため、システム構築費として数十万〜数百万円の初期費用が必要になることが一般的です。
ランニングコストとして保守費用が年間で発生しますが、セキュリティ面を自院で細かく管理できる点がメリットです。多拠点展開や複数診療科を運営している医療法人の中には、オンプレミス型の柔軟性を重視して採用している例があります。導入コストは高いものの、複雑な業務フローにも対応しやすい点が評価されています。
会計ソフトの費用を検討する�際は、レセコン連携や部門別管理などの追加モジュール費用も見落とさないようにしたいところです。クラウド型の場合、連携オプションが月額3,000〜1万円ほど必要になるケースがあります。オンプレミス型では、カスタマイズ費用として一括で追加料金が発生することもあります。
部門別管理や補助金管理機能など、医療特有の処理に関係するモジュールは費用が高くなりやすいため、必要機能の優先順位を明確にしておくと良いでしょう。長期的なコストと運用負担を比較しながら選定することが重要です。
まとめ|医療機関に適した会計ソフトで経営を効率化しましょう
医療機関の会計業務は、診療報酬や補助金の管理、部門別収支の把握など、一般企業とは異なる複雑さがあります。こうした業務に適した会計ソフトを導入することで、入力作業の効率化や財務処理の正確性向上につながり、経営判断に必要なデータも整います。
また、レセコン連携や医療法人会計基準への対応、制度改正へのサポートなど、医療向け機能の有無は導入効果を左右します。自院の規模や業務フローに合ったソフトを選ぶことで、日常業務の負担を減らし、安定した運営に近づけるでしょう。導入メリットと費用を比較しながら、最適な会計ソフトを検討してみてください。
運営に関するお問い合わせ、取材依頼などはお問い合わせページからお願いいたします。