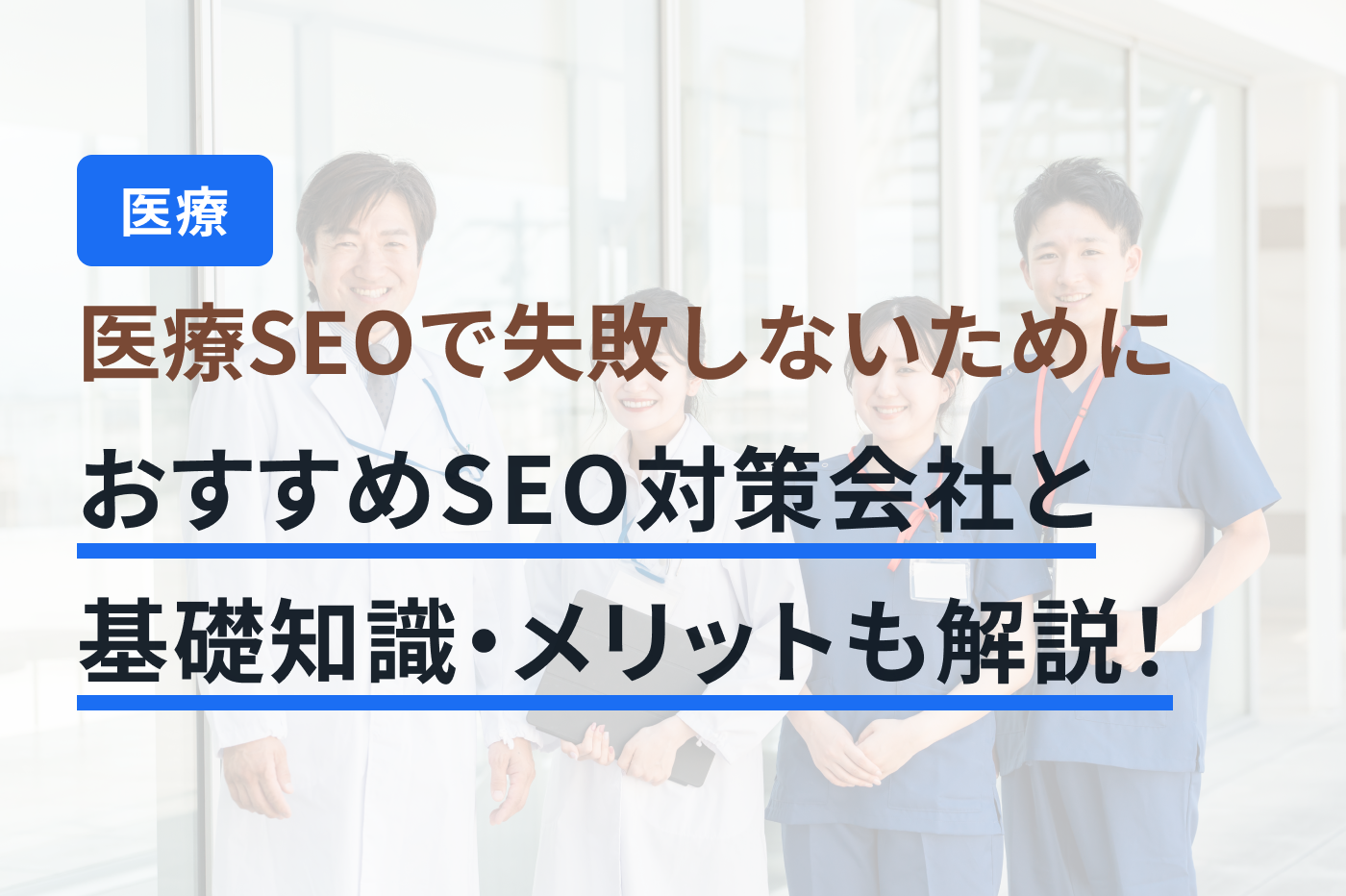製薬会社に強いおすすめの動画制作会社6選!選び方や費用相場、制作事例も紹介
更新日 2025年12月10日
医療業界に強い動画制作会社
診断とヒアリングでお探しします!
製薬会社では、研究開発の成果や製品情報、CSR活動、学術的な説明などを動画で発信する機会が増えています。ただ、薬事規制や専門的な内容の難しさもあって、「どの制作会社に依頼すればいいのか分からない」「医療や製薬分野の実績がある会社なのか判断が難しい」と感じるケースも少なくありません。
そこで本記事では、製薬分野に強いおすすめの動画制作会社を紹介します。さらに、動画制作の選び方や費用相場、制作事例も解説。ぜひ、自社に合った動画制作会社探しの参考にしてください。
目次
製薬会社が動画を活用するメリットと主な活用ケース

製薬会社が動画を活用する最大のメリットは、専門的な情報を「わかりやすく、正確に」伝えられる点にあります。薬の作用機序(メカニズム)や研究成果などは、文章や静止画像だけでは理解しにくい内容も多く、映像化によって直感的な理解を促進できます。また、医療従事者だけでなく一般の生活者にも正しい知識を広める手段として有効です。具体的な活用シーンとしては、以下の例が挙げられます。
- 医薬品のプロモーション動画
- 学会や展示会での研究発表動画
- 社内研修・MR(医薬情報担当者)向け教育動画
- 採用・CSR活動の紹介動画
近年はオンライン学会やウェビナーの普及により、デジタル上での映像コンテンツの重要性が一層高まっています。さらに、動画は再生データの分析によって、視聴時間や離脱率などの定量的な効果測定が可能です。この効果測定によって、メッセージの伝わり方を可視化�し、より効果的な情報発信へと改善できます。製薬会社にとって動画は、正確性と伝達力を両立できる戦略的なコミュニケーション手段といえるでしょう。
製薬会社が動画を活用する際の注意点

製薬会社が動画を活用する際は、法律遵守と情報の正確性が重要です。薬機法や景品表示法のほか、専門性の高い内容に伴う誤解のリスクにも十分配慮する必要があります。加えて、監修体制や情報管理、法改正への対応など、制作後の運用面までを含めた体制構築が欠かせません。
ここからは、製薬会社が動画を活用する際の注意点をご紹介します。
薬機法・景品表示法への準拠
製薬会社が動画を制作・公開する際には、薬機法(旧薬事法)と景品表示法への適正な対応が不可欠です。これらの法律は、医薬品や医療機器の広告表現を規制するもので、虚偽・誇大�な表現や科学的根拠のない訴求を防ぐことを目的としています。違反した場合、行政処分や企業イメージの毀損など、重大なリスクを伴います。
動画は視覚的訴求力が高いため、ナレーションやテロップ、映像演出が薬効を誤解させる恐れがないか慎重に確認する必要があります。特に医療関係者向けと一般向けでは広告規制の範囲が異なるため、目的別に内容を区分して制作することが求められます。
そのため、制作前に法的観点からのシナリオ確認を行い、薬機法を熟知した監修者や法務担当者と連携する体制が重要です。コンプライアンスを徹底したうえで、信頼性と訴求力を両立させることが製薬動画制作の基本姿勢といえます。
誤解を招かない表現と科学的根拠の明示
製薬会社の動画では、正確な情報伝達と視聴者の理解を両立させるために、科学的根拠に基づいた表現が求められます。特に薬効や安全性に関する情報は、誇張や曖昧な表現を避け、第三者が検証可能なデータや研究結果をもとに構成することが重要です。
また、動画の構成や演出によって誤解を招くリスクにも注意が必要です。例えば、映像のテンポや音楽が「治療効果を保証する」ような印象を与える場合、消費者を誤認させるおそれがあります。説明テロップの付与や、科学的根拠を引用するナレーションを取り入れることで、情報の透明性を確保できます。
さらに、専門用語を多用せず、医療従事者だけでなく一般視聴者にも理解しやすい言葉に置き換える工夫も大切です。表現の正確性とわかりやすさのバランスを保ち、視聴者に信頼される情報発信を目指しましょう。
医師・研究者など専門家による監修体制の必要性
動画制作においては、医師や研究者といった専門家による監修体制を整えることが、信頼性を担保するうえで不可欠です。専門家監修の有無によって、動画の正確性・説得力・倫理性が大きく変わります。特に臨床データや薬理情報を扱う場合は、学術的根拠の確認が欠かせません。
監修体制の整備により、制作段階で誤りや不正確な記述を防ぎ、薬機法違反や誤解の発生リスクを最小限に抑えることができます。また、専門家のコメントや監修テロップを明示することで、視聴者に「信頼できる情報源」である印象を与える効果もあります。
さらに、複数領域の専門家を巻き込むことで、疾患領域をまたぐ製品や新規作用機序など、複雑なテーマにも対応可能です。専門家との協働体制を確立し、科学的な正確性と社会的責任を両立させることが求められます。
情報管理と守秘義務への配慮
製薬会社の動画制作では、機密性の高い研究情報や開発中データを扱うことも多く、情報管理と守秘義務への配慮が不可欠です。制作会社との間で秘密保持契約(NDA)を締結することはもちろん、社内外の関係者間でデータ共有を行う際も、アクセス権限の設定やファイル管理のルール化を徹底する必要があります。
映像素材には、まだ公表されていない臨床試験データや製品情報が含まれることがあり、漏洩すれば企業の信用失墜や法的トラブルに発展しかねません。データの取り扱いは、クラウド上の暗号化や社内承認フローを設けるなど、実務レベルでの対策が求められます。
制作会社にも、医療情報の取り扱い経験やセキュリティ体制(ISO27001などの認証有無)が整っているか確認しましょう。
薬機法改正や添付文書改訂に伴う動画公開後の修正対応
医薬品関連の情報は、薬機法改正や添付文書(医薬品の正式な使用説明書)の改訂などにより、内容が頻繁に更新されます。動画を制作して終わりではなく、公開後の修正・更新に対応できる体制を整えておくことが重要です。
特に製品の効能効果・用法用量・副作用情報が変更された場合、旧情報を含む動画を放置すると法的リスクが発生します。改訂内容に応じて速やかにナレーションやテロップ、映像を差し替えられる柔軟な対応力が求められます。
また、制作段階で将来的な修正を想定し、テキストやナレーション部分を別データで管理しておくと効率的です。更新履歴を明確にし、最新版の�情報発信を継続できる仕組みを構築することで、長期的に信頼性の高い動画運用が可能になります。
医療業界に強い動画制作会社
診断とヒアリングでお探しします!
製薬会社が動画制作会社を選ぶ際のポイント

製薬業界では、専門知識と法的理解を兼ね備えた制作会社を選ぶことが重要です。単に映像技術が優れているだけでなく、医療業界特有のルールや学術的正確性を理解しているかが重要な判断基準となります。
ここからは、製薬会社が動画制作会社を選ぶ際のポイントを紹介します。複雑な内容を「専門的かつ分かりやすく」映像化できるパートナーを選定しましょう。
医療・製薬分野での実績の有無
製薬会社の動画は、医療・製薬分野での制作実績が豊富な会社を選ぶことが重要です。一般企業のプロモーション映像とは異なり、専門知識と精密な情報設計が求められます。過去に医薬品の作用機序や臨床研究紹介、医療機器の説明動画などを手掛けた経験があれば、医療表現の正確さや薬機法への意識も高いと判断できます。
実績のある制作会社は、専門家とのコミュニケーションにも慣れており、用語選定や構成においても精度の高い提案が可能です。また、学会動画や患者啓発向けコンテンツなど、目的に応じた映像スタイルの最適化にも長けています。過去の制作事例を確認し、自社の目的に近い実績を持つ会社を選ぶとよいでしょう。
規制対応に精通したディレクション力
製薬会社の動画制作では、薬機法や景品表示法、個人情報保護法など、複数の法規制を正確に理解し運用する必要があります。ディレクターがこれらの法的枠組みに精通しているかどうかが、プロジェクトの成否を大きく左右します。単に映像を仕上げるだけでなく、「何を表現してよいか・どの表現は避けるべきか」を判断できる知識が不可欠です。
規制対応に強い制作会社は、初期の企画段階から法務・薬事担当者との調整を行い、表現リスクを未然に防ぎます。さらに、社内承認プロセスを理解して進行管理を行うため、確認作業もスムーズです。コンテンツ公開後に指摘を受けるリスクを軽減できる点でも、信頼性の高い制作体制といえます。動画制作を依頼する際は、ディレクターの医療系案件経験や法規対応の知識レベルを確認しましょう。
3DCGやアニメーションによる専門的表現力
製薬業界では、薬の作用機序(MOA)や細胞レベルでの動きを可視化する必要があり、3DCGやアニメーションによる表現力が欠かせません。これらの技術を活用することで、複雑な生理学的プロセスを直感的に理解させる映像表現が可能になります。特に研究発表や教育用コンテンツでは、論文やグラフだけでは伝わ��りにくい情報を映像で補う効果が期待できます。
3DCG制作には、科学的知識とデザイン力の両立が求められます。例えば、分子の結合や薬剤の作用部位をリアルに再現する際、専門的な監修のもとで精密にモデリングを行うことが重要です。さらに、CG表現のクオリティだけでなく、視聴者に「どのように作用するか」を明確に伝える構成力も評価すべきポイントです。医療系アニメーションに特化した制作会社を選ぶことで、正確性と訴求力の両立が実現できます。
「3DCG」:コンピュータ上で縦・横・奥行きの3方向を表現し、立体的な画像や動画を生成する技術の総称
学会・セミナー配信用の制作ノウハウ
学会や医療セミナー向けの動画は、一般的なプロモーション映像とは異なる制作ノウハウが求められます。特に発表時間の制約やスライド構成、音声収録などの要件を満たすには、発表者の専門性や研究内容を正確に伝えるための編集力と、聴衆が理解しやすいテンポ設計が不可欠です。また、医療業界特有のルールや知識の理解も求められます。
学会配信に対応した制作会社は、字幕や多言語対応、配信プラットフォームとの連携などにも長けています。また、現地収録から編集・納品までのスピード感も重視されるため、ワンストップで対応できる体制を持つ企業が理想です。オンライン・ハイブリッド開催が増える中で、安定した配信品質を維持できる制作会社は大きな強みを持っています。医療研究の発信を支えるパートナーとして、学会対応経験は必ず確認しましょう。
薬機法対応チェックの再依頼や、学会用の追加編集などの対応力
製薬会社の動画は、薬機法対応の再チェックや追加編集が必要になるケースが多いため、一度納品して終わりではなく、柔軟に対応してくれる制作会社を選ぶことが重要です。例えば、薬事審査部門の確認後に表現修正を求められたり、学会発表用に字幕やナレーションを差し替えるケースも少なくありません。
修正対応力の高い会社は、データ構造を整理して管理しており、部分的な再編集が効率的に行えます。また、修正内容に対しても迅速に見積もり・納期を提示できる体制を整えていることが多いです。薬機法や医療広告ガイドラインの改正にも対応し、最新の基準に基づいて再監修を行える会社であれば、長期的なパートナーとして信頼できます。継続的な運用を見据え、更新・修正体制を確認しておきましょう。
医療業界に強い動画制作会社
診断とヒアリングでお探しします!
製薬会社に強いおすすめの動画制作会社6選
ここからは、製薬会社におすすめの動画制作会社を厳選してご紹介します。それぞれの強みや特徴を踏まえて、自社にあったホームページ制作会社を探してみてください。
1.合同会社 faba

faba 合同会社は、東京都渋谷区に位置するメディカルコミュニケーション専門の制作会社です。医療従事者が必要とする知識をコンテンツとして提供し、製薬メーカーが伝えたいことをサポートしています。経験豊富なクリエイターが揃い、コスト削減や時間短縮を実現しながら、質の高いサービスを提供しています。
合同会社 fabaの特徴
- 各分野の経験豊富なクリエイターが在籍し、高品質なコンテンツ制作を実現。
- 映像制作からグラフィックデザイン、アプリ開発まで、幅広いサービスを提供。
- 小さな依頼でも対応可能で、見積もり相談も受け付け。
- 医薬・医療分野に特化したコンテンツ制作により、専門性と表現力を両立。
URL | |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-23-4 kuwano BLD 2F |
2.株式会社ライルピクチャー

株式会社ライルピクチャーは、東京都千代田区に本社を構える医療映像専門の制作会社です。医療現場に特化したインフォームドコンセント動画の制作や、医療機器のプロモーション動画などを手がけており、医師の説明負担軽減や患者の理解促進を目的としたサービスを提供しています。最新の映像技術を活用し、効率的で効果的な医療コミュニケーションを実現しています。
株式会社ライルピクチャーの特徴
- 医療に特化した映像制作を行い、専門的なニーズに応える。
- 医師の説明時間を効率化し、患者の理解を深めるための動画を提供。
- クライアントの負担を減らすための新しい制作スタイルを提案。
- 医療現場のニーズに応じたカスタマイズが可能な動画制作。
- 医療機器やサービスの魅力を短時間でアピールすることができる。
URL | |
所在地 | 東京都千代田区神田神保町1-2-10 5F |
3.株式会社サムシングファン

サムシングファン株式会社は、大阪、東京、名古屋に拠点を持つ動画制作・映像制作会社で、年間7,000本以上の映像制作実績を誇ります。「価値を映す」をテーマに、動画DX®の提案を行い、企業のブランディングやマーケティングを支援しています。豊富な経験と技術力を活かし、顧客のニーズに応じたオリジナル映像コンテンツを提供します。
株式会社サムシングファンの特徴
- 動画を活用したマーケティングやブランド戦略を提案。
- 年間7,000本以上の映像制作実績があり、多様な業界に対応可能。
- オンラインで完結する動画制作サービスを提供し、柔軟な対応を実現。
- ドローン撮影、ライブ配信、アニメーション動画など、幅広いサービスを展開。
- 動�画マーケティング支援ツールを活用し、効果的な映像分析を実施。
URL | |
所在地 | 東京都千代田区神田錦町3-1 オームビル本館2階 |
4.株式会社アトムストーリー

株式会社アトムストーリーは、様々な動画コンテンツやマーケティング施策を通じて、顧客のニーズに合わせた独自のスト��ーリーを提供します。ストーリーマーケティングを専門とする企業で、累計2000本以上のパラパラ漫画を制作している日本一の実績を誇ります。「考える」「つくる」「届ける」をモットーに、コンテンツ制作とともに顧客のビジネスの成果を最大化することに注力しています。
株式会社アトムストーリーの特徴
- 消費者ニーズの調査から企画まで、包括的なマーケティング戦略を提供。
- アニメーションムービー、ロールプレイングムービーなど、豊富な制作メニュー。
- プレスリリース作成、広告運用、SNS運用に対応。
- 実績に基づいた顧客のフィードバックを取り入れ、サービス改善を図る。
URL | |
所在地 | 東京都港区南青山3-1-36 |
5.株式会社プルークス
株式会社プルークスは、東京都代々木に本社を置くデザイン制作会社で、WEB・紙媒体・動画制作を中心に活動しています。「あたりまえのコトをあたりまえに」という理念のもと、高品質なデザインと丁寧なコミュニケーションを重視し、企業や個人のニーズに応じた様々なサービスを提供しています。
株式会社プルークスの特徴
- WEB、紙媒体、動画を組み合わせた効果的な提案が可能。
- 納期厳守、丁寧な打ち合わせ、社内校正の徹底により、確かな品質を提供。
- 引き継ぎ案件にも対応し、要望に応じた柔軟なデザイン制作。
- 課題解決に向けた多様なプランを提案。
- Pマークを取得し、顧客データの安全性を確保。
URL | |
所在地 | 東京都中央区日本橋大伝馬町14-17大伝馬町千歳ビル4階 |
6.Crevo株式会社

Crevo株式会社は、東京を拠点とする動画制作会社で、2,000社以上の顧客に対して10,000件以上の動画制作実績を誇ります。主に企業��プロモーション、採用動画、商品紹介など多岐にわたる映像制作を行い、戦略的な企画提案と高品質な制作を通じて顧客のビジネス成果を実現します。動画の制作だけでなく、運用や分析・効果検証まで一貫してサポートする体制を整えています。
Crevo株式会社の特徴
- 2,000社・10,000件以上の制作実績を持つ。
- 動画制作に加え、動画マーケティング、SNS運用、サイト・LP制作まで対応。
- 顧客のビジネス課題に基づいた最適な動画制作を提案。
- 企画から納品までの全プロセスを一貫して提供。
- アニメーション、実写、3DCG動画など、ニーズに合わせた制作が可能。
URL | |
所在地 | 東京都港区六本木4丁目8-5 和幸ビル502 |
医療業界に強い動画制作会社
診断とヒアリングでお探しします!
製薬会社の動画制作の平均費用相場は「50〜150万円」ほど

製薬会社の動画制作費は、内容の専門性や演出方法によって大きく異なります。一般的なプロモーション動画であれば50〜150万円程度、作用機序を3DCGで表現する場合は200〜400万円前後が相場です。学会発表用や海外向けの多言語対応動画など、特殊要件が加わるとさらに費用が上がる傾向があります。
費用の差を生む要因は、「監修体制」「アニメーション技術」「ナレーション・翻訳」「法規対応コスト」などです。医療業界では、薬機法チェックや監修工程が必須のため、一般的な企業よりもコストがかかる点を理解しておく必要があります。
コストを抑えたい場合は、既存映像素材を再編集する、あるいはモーショングラフィックスを用いて簡易的に再現するなどの工夫をしましょう。重要なのは、単に安さで選ぶのではなく、「正確性と信頼性を担保できる制作体制」に見合った予算を設定することです。
製薬会社による動画活用の成功例

製薬会社では、研究発信からブランディングまで幅広い目的で動画が活用されています。ここでは、動画を効果的に活用して成果を上げた成功例を紹介します。作用機序の理解促進や社内教育など、目的に応じた動画制作の方向性を検討する際の参考にしてください。
製品理解を促進した作用機序動画の成功例
第一三共は、自社サイトや動画ギャラリーでコンセプトムービーや製品ストーリー動画を制作しており、製品理解を目的とする映像発信に注力しています。例えば、第一三共の「Medi Theater」シリーズでは、鎮痛薬ロキソニンの開発秘話や作用機序をメディカル視点で解説する動画を公開しています。
これにより、一般ユーザーや医療関係者に「なぜこの薬が効くか」を訴求し、ブランド理解を促進する狙いがあります。
また、第一三共の「動画ライブラリ」には、医療関係者向けに製品の臨床データや作用説明を解説する「バーチャル製品説明会」動画が多数収録されており、医師・薬剤師が視聴しやすい形式で提供されています。
このような動画活用により、複雑な作用機序を視覚的に理解してもらう機会を拡充し、製品理解をサポートするモデルになっています。
研究成果を広めた学術発表動画の成功例
医薬品や治療法に関する研究成果を広く共有するには、学会発表だけでなくデジタル動画も活用されています。例えば、第一三共の医療関係者向けサイト「Medical Community」では、各製品について学術的講演動画や臨床成績を扱う「Web講演会」動画を公開しています。
これらの動画では、スライド資料に加えナレーションやグラフィックを重ねて情報整理し、視聴者が主張やデータの構造をつかみやすくしています。
また、こうした動画を海外学会向けに多言語字幕付きで展開すれば、グローバル発信にもつながります。制作会社と連携して、専門用語の訳語や統計表現の適切性を担保した動画を作ることで、発表者の信頼性を維持しながら知見を広く伝える役割を果たせます。
社内研修・MR教育で効果を上げた動画活用成功例
公開情報として、社外に「社内教育用動画」の具体例を明示している例はありませんが、傾向として、MR(医薬情報担当��者)向け教育や導入研修で動画活用が進んでいると考えられます。
例えば、動画教材として製品知識、倫理・法令順守、情報提供技術などをモジュール化して映像化し、全国拠点で共通の視点を持たせるケースがあります。
また、社内研修用動画ではクイズやケーススタディ、ロールプレイを組み込む形式も多く用いられ、視聴者の理解度に応じた追加コンテンツ配信が可能です。
これらを導入した企業は、教育の標準化やコスト削減、受講履歴管理・分析の整備という成果を期待しており、動画を中心とした研修体系を推進しています。
ブランド認知向上につながったCSR動画の成功例
武田薬品は、企業理念や社会貢献活動を示すブランディング動画/CMを制作する取り組みを行っており、CSR・ブランド認知強化に活用しています。例えば、武田薬品は企業ブランディングキャンペーン「世界に尽くせ、タケダ。革新的に。誠実に。」の一環として、動画やCMを通じて「ダイバーシティ」や社会と研究開発の関係などを表現してきました。
また、武田のグローバルCSRプログラムでは、途上国での保健制度強化や医療アクセス改善をテーマとした活動を多数実施しており、これらの活動紹介動画を通じて企業の社会的使命を伝える基盤となっています。これにより、医療業界内外のステークホルダーや一般市民に対して企業の価値観を可視化し、ブランド信頼を高める効果が期待されています。
まとめ|信頼性と表現力を両立した動画制作で製薬の魅力を届けましょう
製薬会社の動画制作では、正確性・透明性・専門性の3要素が重要です。薬機法への準拠や科学的根拠の明示といった法的責任を果たしつつ、視聴者に伝わる映像表現を追求することで、医療の信頼を守りながらブランド価値を高められます。
また、3DCGやアニメーションを活用すれば、複雑な研究内容や作用機序もわかりやすく可視化できます。さらに、学会配信・社内教育・CSR発信など、多様な目的に応じて映像の活用範囲を広げることも可能です。
信頼性を担保しながら専門性を伝える動画は、製薬業界における最も効果的なコミュニケーション手段のひと��つです。適切な制作パートナーと協働し、正確かつ魅力的に医薬の価値を伝えていきましょう。
医療業界に強い動画制作会社
診断とヒアリングでお探しします!